“ただ作るだけ”はもう古い。お客様に選ばれるパンフレット制作の流れと秘訣
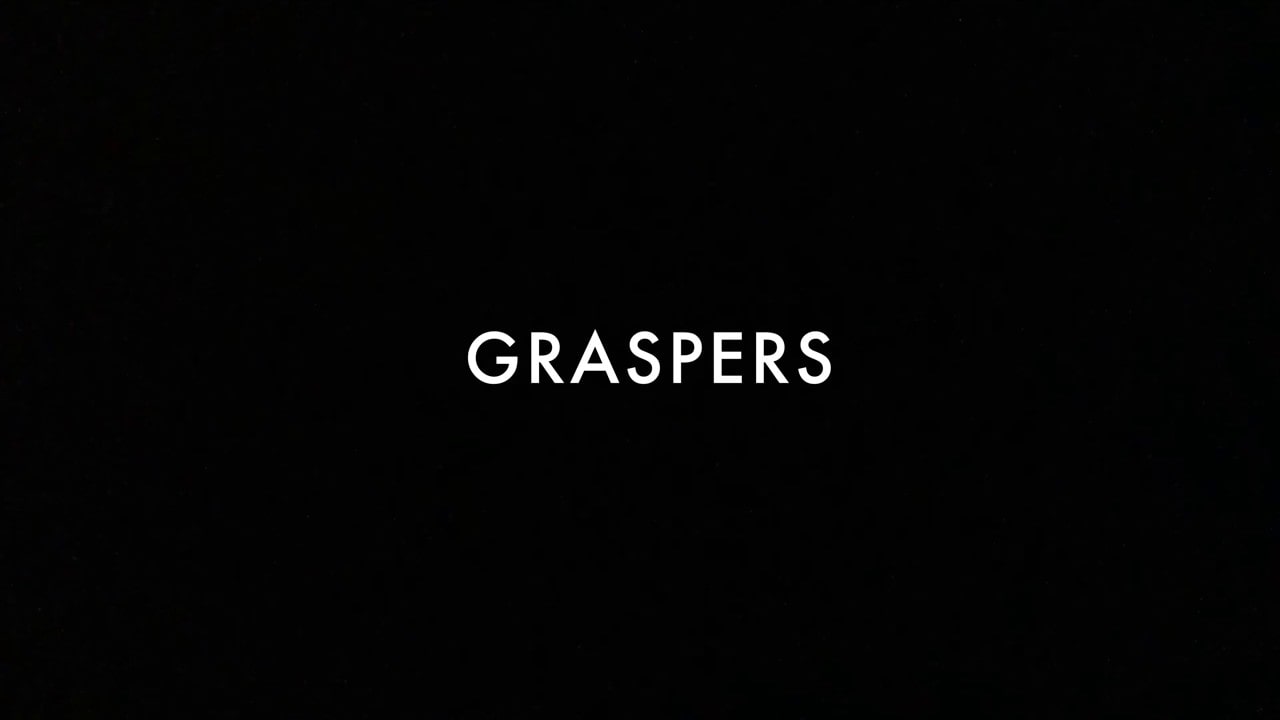
目次
-
「作ること」が目的ではなく「成果」を出すためのパンフレット
-
パンフレット制作の流れとポイント
-
実際に喜ばれた3つの工夫
-
パンフレットは営業ツールとして進化させるべき理由
目次
「作ること」が目的ではなく「成果」を出すためのパンフレット
パンフレットは単なる“資料”ではありません。イベントや商談、展示会、店舗での手渡しなど、あらゆる接点で「信頼を勝ち取る営業マン」のような役割を果たすツールです。しかし、よくあるのが「とりあえず作って配ったけれど反応が薄かった」という声。なぜ反応が薄いのか。それは「見た目を整えること」がゴールになってしまっているからです。本当に必要なのは、成果につながる構成力と、受け取った人の心を動かすストーリー設計です。それを実現するのが私たちのパンフレット制作の流れです。
パンフレット制作の流れとポイント
-
ヒアリングでゴールを共有
制作の出発点は「なぜ作るのか」を徹底的に聞くことです。配布シーン、ターゲット、期待するアクション(問い合わせ・来店・注文など)を明確にし、ただの説明資料ではなく“成果を生む武器”になる設計を行います。 -
構成とストーリー設計
次に行うのは、内容の構造化です。よくあるパンフレットは情報が並んでいるだけですが、私たちは「順序立てたストーリー」で読ませます。たとえば、まず課題提起、次に解決策、そして信頼感を高める実績紹介、最後にアクションの促し――この流れを意識し、読んだ人が「この会社に頼みたい」と思う導線を作ります。 -
デザインで“読みたくなる”をつくる
ただ情報を詰め込むだけでは、人はパンフレットを読み進めてくれません。だからこそ、視線の動きをコントロールするデザイン設計、余白の使い方、色彩の心理効果まで細かく意識しています。 -
校正とブラッシュアップ
初稿を出して終わりではありません。実際の使われ方やお客様の声をもとに微調整を重ね、「配って終わり」でなく「配った後の成果」にこだわります。
実際に喜ばれた3つの工夫
私たちが手がけたパンフレット制作で、お客様から特に高く評価された工夫を3つ紹介します。
-
ストーリーで“読む理由”をつくった
単にサービスを説明するのではなく、「なぜこのサービスが必要なのか」「その先にどんな未来があるのか」を物語として見せたことで、商談の場で話の流れを作りやすくなったと評価いただきました。 -
余白と視線設計で「読みやすい!」と言われた
「情報を詰め込みすぎない勇気」を持ち、あえて余白を活かしたデザインにしたことで、「一目で内容が入ってくる」と多くの方から反応がありました。 -
配布シーンに合わせたサイズ感と仕様
展示会ならバッグに入れやすいA5サイズ、役員向けの高級商談なら厚手の紙とマット加工、ターゲットに応じて仕様まで工夫し、配りやすく、印象に残る仕上がりにしました。
パンフレットは営業ツールとして進化させるべき理由
今やパンフレットは「会社案内の補足」ではなく、「営業・広報・ブランディングの最前線ツール」です。オンラインとオフラインが融合する時代だからこそ、手に取ったその瞬間の印象が、その後の検索行動や問い合わせ、来店に直結します。見た目の美しさ以上に、「読ませる力」「信じさせる力」「動かせる力」が問われる時代です。“ただ作るだけ”のパンフレットから、“成果を生む”パンフレットへ。私たちはこれからも、その実現にこだわり続けます。



