そのデザイン、本当に使いやすい?美しさと機能性の間で揺れる現場のリアル
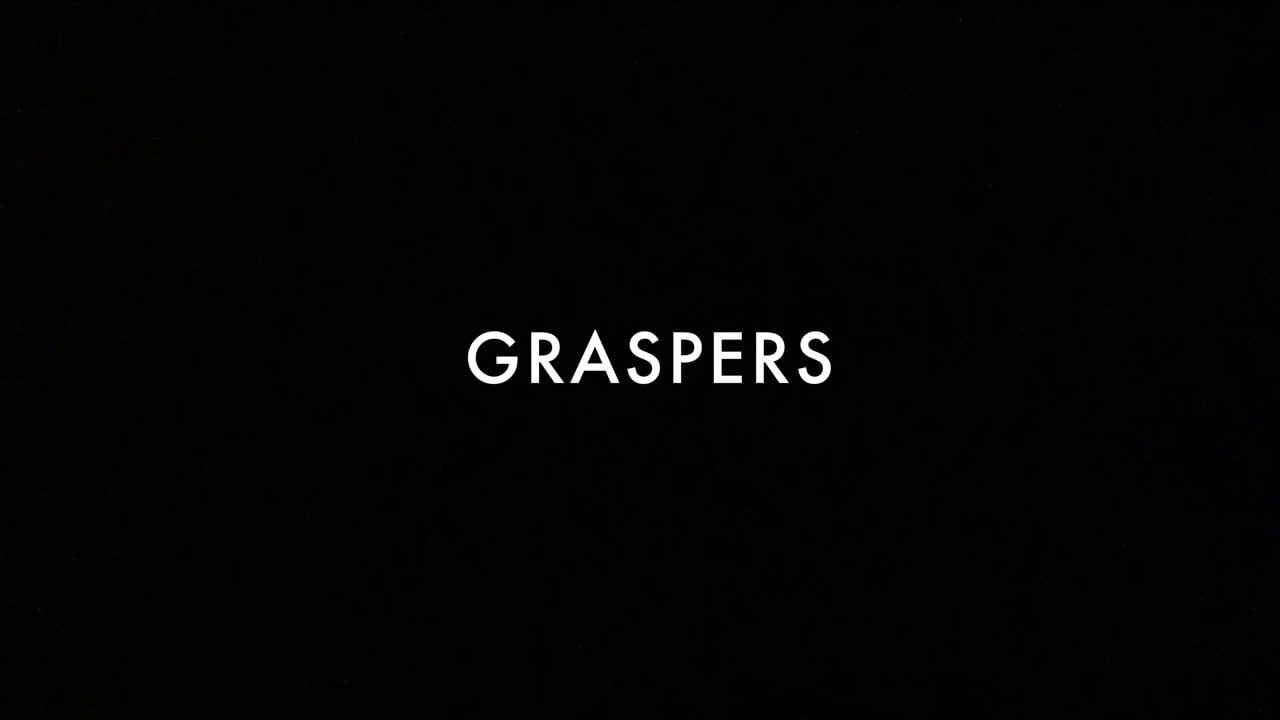
目次
-
デザインと使いやすさは同じではない
-
見た目の美しさだけを追ったデザインの落とし穴
-
使いやすさを意識しすぎた結果、魅力が消えることも
-
議論の着地点は「目的を軸にしたデザイン」
-
使いやすさとデザイン性を両立させるために必要な視点
目次
デザインと使いやすさは同じではない
デザインと聞くと、つい「美しいものを作ること」と考えがちですが、実際の現場では「デザイン=見た目の美しさ」と「デザイン=使いやすさ」はしばしば対立します。私たちの社内でも、「もっと洗練させたい」という声と、「とにかくわかりやすく使いやすく」という声がぶつかることがあります。どちらも正しい。でも、そのバランスが難しい。デザインとは、単に飾ることではなく、相手の行動を後押しするための手段であり、その意味で使いやすさと美しさはどちらも欠かせない要素なのです。
見た目の美しさだけを追ったデザインの落とし穴
「このデザイン、かっこいいけど…どこを押せばいいかわからない」。そんな経験、誰しも一度はあるのではないでしょうか。フォントはおしゃれ、色もスタイリッシュ、画像も洗練されている。だけど、どこがリンクかわからない、ボタンが目立たない、文字が小さくて読みにくい――そんなデザインは、せっかくのビジュアルの良さが逆にストレスを生み、ユーザーの離脱を招いてしまいます。デザインの美しさだけを優先したときに陥りがちな落とし穴です。
使いやすさを意識しすぎた結果、魅力が消えることも
一方で、「誰が見ても迷わないように」「とにかく情報がすぐ見えるように」と使いやすさを重視しすぎるあまり、無難で個性のないデザインになってしまうこともあります。結果として、見た目のインパクトが薄れ、ブランドの世界観やサービスの魅力が伝わりにくくなってしまう。特に競合が多い業界では、「見た目で興味を引く力」は決して軽視できない要素です。シンプルさを求めるあまり、“選ばれる理由”を失ってしまう。これもまた、私たちが議論の中で直面する課題です。
議論の着地点は「目的を軸にしたデザイン」
このテーマに正解はありません。ただ、私たちが大切にしているのは、「目的に立ち返ること」です。そのデザインは、何のためのものなのか。問い合わせを増やすためか、認知を広げるためか、ブランドの価値観を伝えるためか。目的が明確になれば、デザインと使いやすさのバランスのとり方も見えてきます。たとえば、第一印象で選ばれることが重要なら、多少操作が複雑でもデザイン性に振り切ることもあります。一方で、商品購入の導線であれば迷わず操作できる使いやすさを最優先にします。議論のゴールは「どちらを取るか」ではなく「目的に最も合ったバランスを探ること」なのです。
使いやすさとデザイン性を両立させるために必要な視点
使いやすさとデザイン性を両立させるには、第三者視点が不可欠です。つまり、「ユーザーがどう感じるか」を徹底的に想像すること。そして、自分たちの理想やこだわりを一度横に置き、実際の使われ方をテストし、フィードバックを素直に受け入れることです。私たちの社内でも、社内外のテストユーザーに触ってもらい、「どこで迷った?」「どこが心地よかった?」をヒアリングしながら改善を重ねています。美しさのために使いやすさを犠牲にしない。使いやすさのために魅力をあきらめない。そうした意識と努力の積み重ねが、デザインと機能が融合した成果物を生みます。



