あのときの“失敗”が教えてくれた、デザインの本当の力
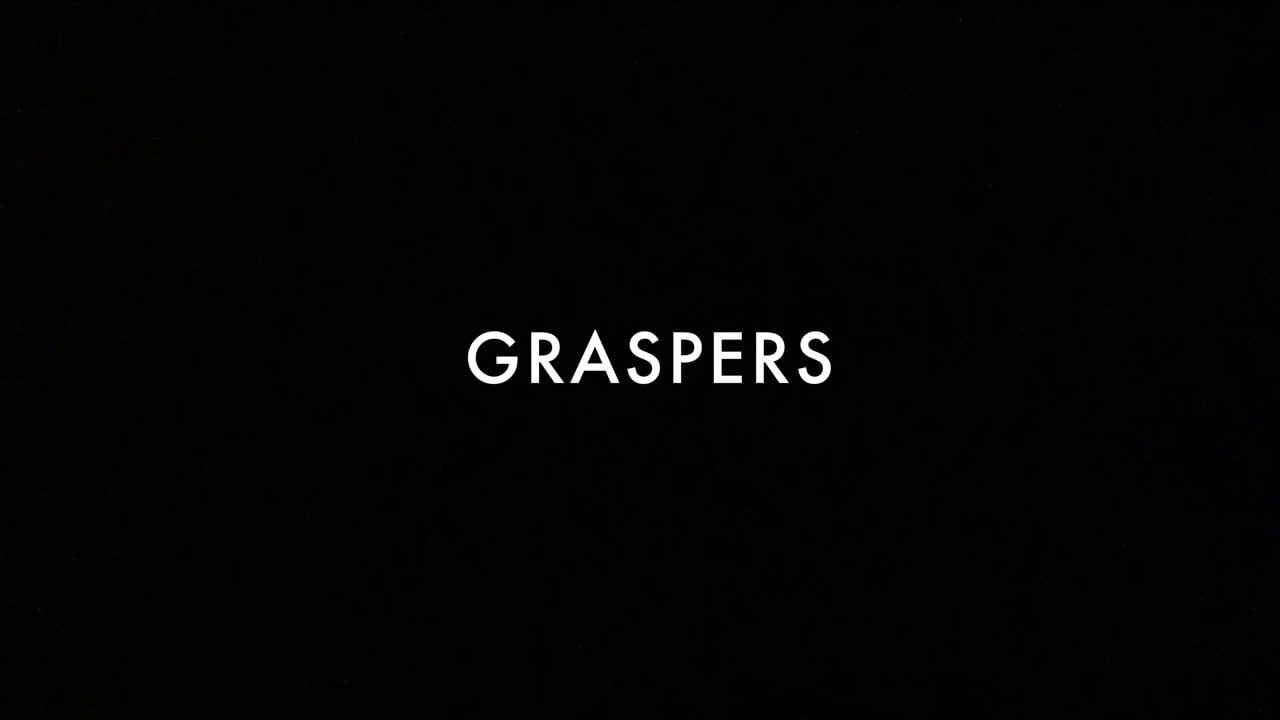
目次
どんな現場にも、学びがある
ものづくりの現場には、いつも正解があるわけではありません。クライアントの想いを形にしようと全力で向き合っても、時には「想像していたのと違った」と言われることがあります。恥ずかしい話ですが、うまくいかなかったプロジェクトからこそ、今に活きる学びがありました。今回はそんな“制作の裏話”を少しだけお届けできたらと思います。
伝わらなかったロゴ。私たちの見落とし
ある時、とある企業ロゴのご依頼をいただきました。ブランドの理念や社風を丁寧にヒアリングし、モチーフや色も慎重に選び、満を持して初稿を提出。けれど返ってきた反応は、「なんだか冷たい印象に見えてしまう」というものでした。意図としては“スタイリッシュ”を狙っていたのですが、相手が求めていたのは“安心感”だったのです。ヒアリング内容を受け取る私たちの“解釈”が、少しずれていたんですね。そこからはとにかく「言葉に頼らず空気感も感じ取る」ことを意識するようになりました。
色で誤解を生んだパンフレットの話
また別の案件では、パンフレットの配色が予想以上に“派手すぎた”と指摘を受けたこともあります。華やかで元気な印象を出そうと、ビビッドなオレンジを多用したのですが、対象となる年齢層の方にとっては「落ち着きがない」と捉えられてしまいました。こちらの意図と、見る側の感性にズレがあったとき、いかに想像力を働かせるかが大事だと痛感したエピソードです。
時間に追われた結果、質が揺らいだ案件
どれだけ経験を積んでも、「急ぎで!」という案件が重なると、どうしても仕上がりのバランスを保つのが難しくなるときがあります。ある時、納期が非常にタイトなチラシ制作において、初稿段階で確認漏れが重なってしまい、修正が連鎖的に発生。結果、クライアントとの信頼関係にも小さなひびが入りました。「納期に間に合わせる」だけでなく、「その中でどうクオリティを守るか」がチーム全体での反省点となりました。
失敗は、チームの絆を深める瞬間でもある
こうした失敗は、その瞬間はつらいものです。でも、どの出来事も社内ではしっかり共有し、次にどう活かすかを話し合ってきました。ミスを一人の責任にせず、みんなで受け止めて次につなげる。そうすることで、「あのときの経験があったから今がある」と言えるチームになれたと思っています。ミーティングで笑い話として話せるようになったとき、成長の証だなと感じます。
これからも、丁寧な対話と見落とさない観察力を大切に
デザインは、“伝える”ことが仕事です。けれど、私たち自身が伝わっていなかったら意味がない。そのことを何度も思い知らされてきました。だからこそ、ヒアリングで出てきた言葉の“奥”にある気持ちや空気も、丁寧に受け止めたい。観察して、読み取って、必要なときは言葉にして返す。そんな地道な姿勢を、これからも大切にしていきたいと思います。



