情報量が多くても伝わる、Webデザインの工夫とは
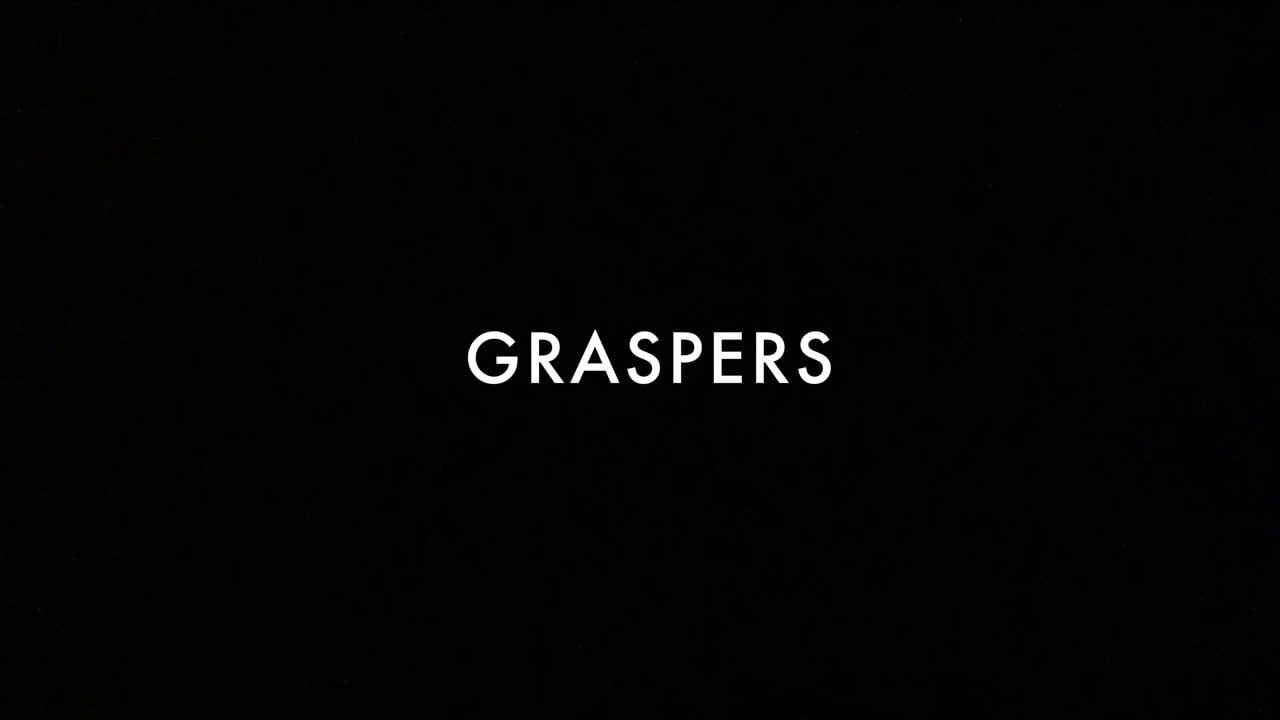
目次
膨大な情報を扱うサイトの課題
コーポレートサイトや公共機関、ECサイトなど、扱う情報が膨大なWebサイトでは、ページ数やカテゴリが多いために「見にくい」「迷う」といった声が寄せられやすくなります。情報を多く詰め込んでいるにもかかわらず、ユーザーに伝わらない。これは単にコンテンツ量の問題ではなく、“見せ方”に課題があるケースが大半です。情報が多いからこそ、設計とデザインの工夫が問われるのです。
情報設計の第一歩は「整理」から
大量のコンテンツを扱う場合、まずやるべきは「情報の棚卸し」です。コンテンツの目的、対象ユーザー、優先順位を明確にした上で、情報を分類・整理していきます。たとえば大学の公式サイトでは、学部情報、受験案内、研究活動、在学生向け情報など、ターゲットが多岐にわたります。こうした情報を「目的別」「対象者別」に分類し、ユーザーの視点でナビゲーションを設計することが重要です。構造設計がしっかりしていれば、膨大な情報も迷わずアクセスできるようになります。
見やすさを担保するデザインのポイント
デザインの工夫によって、情報の伝わりやすさは大きく変わります。たとえば以下のような要素は、情報量が多いサイトで特に重要です。
-
グリッドレイアウト:整った見た目で視線誘導がしやすくなる
-
色や余白の使い方:重要情報に視線が集まりやすくなり、可読性が向上
-
アイコンや図解の活用:文章では伝わりにくい内容も直感的に理解される
また、情報の「階層」を意識して見出しを設けたり、アコーディオン形式で表示を制御したりすることで、ページ全体の見通しが良くなります。
レスポンシブ対応でユーザー体験を最適化
現代のWebサイトは、スマートフォンやタブレットなど、あらゆるデバイスでの閲覧が前提です。特に情報量が多いサイトでは、レスポンシブデザインによって、どの画面サイズでも快適に情報を得られるようにする必要があります。
ある調査によると、モバイルフレンドリーでないサイトは、訪問者の60%以上が直帰する傾向があるとされています(出典:Think with Google – Mobile Site Design)。コンテンツが豊富でも、閲覧がしにくければ意味がありません。階層構造を簡略化し、メニューをモバイル仕様に調整するなど、端末ごとに最適化された体験設計が求められます。
実際に評価されているサイトの特徴
膨大なコンテンツを美しく見せているWebサイトの代表例として、以下のような特徴が挙げられます。
-
NHK公式サイト:高い情報量を持ちながら、ニュース、番組、特集コンテンツを明快に分類。余白を活かした見やすい設計が特徴。
-
Apple公式サイト:製品ごとに整然とした階層があり、情報は豊富だが導線はシンプル。デザイン性と機能性の両立を実現。
-
楽天市場の特集ページ:膨大な商品数をフィルタやカテゴリでスマートに分類。情報密度を感じさせない工夫がある。
これらのサイトはいずれも、単に“おしゃれ”なだけでなく、ユーザーが情報にたどり着きやすい構造設計とビジュアル設計を両立させています。
情報を魅せるデザインで競合に差をつける
経営者やスタートアップ事業者にとって、自社サービスや事例紹介、採用情報など、多くの情報をWebで発信する必要がある場面は少なくありません。その際、ページ数が増えたりコンテンツが煩雑になったりすると、ユーザーの離脱リスクが高まります。だからこそ、「整理して伝える」「視覚で理解させる」デザインが武器になります。
情報量をネガティブに捉えるのではなく、きちんと“魅せる”設計ができれば、それは競合との差別化要素になります。ユーザーの行動を先回りし、ストレスなく情報にたどり着ける設計は、それ自体が企業の信頼感や先進性を伝えるメッセージにもなるのです。



