伝える力を形にする──“デザインの本質”を見直そう
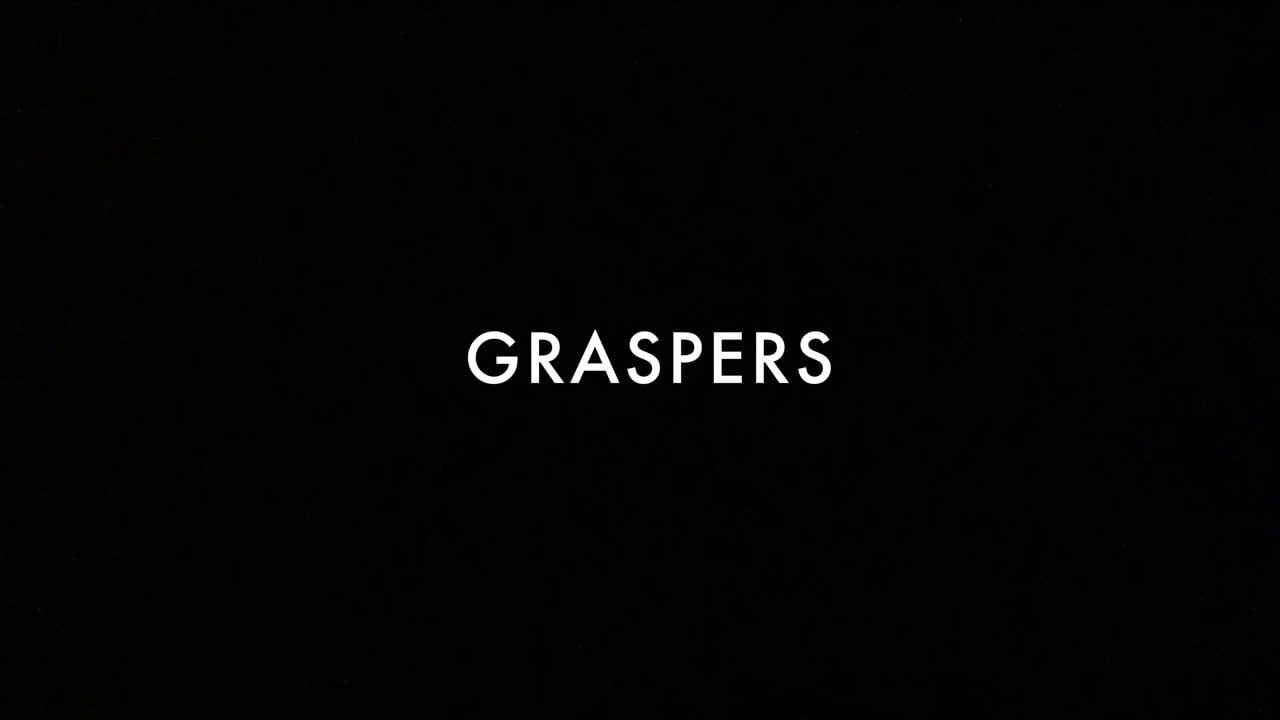
目次
デザインは見た目ではなく「意図」の表現
「デザイン」と聞くと、整った見た目やスタイリッシュな印象を思い浮かべる人も多いでしょう。しかし、デザインの本質は“見た目を整える”ことではありません。本来のデザインとは「課題を解決するための設計」であり、伝えたい意図を最も効果的なかたちで表現する手段です。見た目の美しさはその一部に過ぎず、あくまで“伝える”ための手段にすぎません。
なぜ経営やビジネスにデザインが関わるのか
経営やビジネスにおいても、デザインの考え方は不可欠です。たとえば、商品のパッケージ、Webサイトの構成、採用パンフレットのレイアウトなど、企業の活動には「何をどう伝えるか」が常に求められます。ハーバード・ビジネス・レビューによると、「デザインを経営に取り入れている企業は、株価の成長率が平均で200%を超えている」という調査結果もあります(出典:Harvard Business Review, 2020)。これは、デザインが顧客体験を左右し、ビジネス価値に直結する証拠です。
本質的なデザインとは「誰に・何を・どう伝えるか」
本質的なデザインとは、以下の3点を明確にすることから始まります。
-
誰に:ターゲットは誰か?年齢、性別、関心、価値観など
-
何を:最も伝えたいメッセージや価値は何か?
-
どう伝えるか:その人にとって分かりやすく、響く方法は何か?
たとえば、若年層向けのブランドでは、ポップでカジュアルなデザインが効果的かもしれません。一方、医療や法律などの分野では、信頼感と正確さを重視した構成が求められます。「誰に向けたものか」によって、色使いもフォントもトーンもまったく変わってくるのです。
具体例に見る“機能するデザイン”の特徴
ある地域密着型の不動産会社が、チラシデザインをリニューアルした事例を紹介します。以前は“おしゃれ”なフォントと写真を多用していたものの、高齢者層には「読みにくい」「わかりづらい」と評判が悪く、反響も低迷していました。そこで、文字サイズを大きく、色数を減らし、図解を中心としたレイアウトに変更したところ、1ヶ月で問い合わせ数が2.3倍に増加したそうです。
ここでのポイントは、「デザイン性を高めた」ことではなく、「伝わるデザインに変えた」という点です。これはあらゆる業種に通じる、本質的な考え方です。
スタートアップが陥りがちなデザインの誤解
スタートアップやスモールビジネスでは、限られたリソースの中で「かっこいい」デザインを重視するあまり、ユーザーの視点を見失うことがあります。ロゴに凝りすぎて読みづらくなったり、写真や色を詰め込みすぎて情報の優先度が曖昧になったり──こうした事例は少なくありません。
デザインは「自己表現」ではなく「他者への伝達」です。特に起業初期の段階では、“好き”や“こだわり”よりも、「ユーザーがどう感じるか」を最優先にすべきでしょう。
本質的なデザイン力をどう身につけるか
では、どうすればデザインの本質を理解し、実務に活かせるようになるのでしょうか。大切なのは、次のような視点を持つことです。
-
目的を常に意識する:「何のためのデザインか?」を言語化する
-
ユーザー視点で考える:自分ではなく、相手の目線に立つ訓練を重ねる
-
情報設計に時間をかける:構成・配置・順序が伝わり方を左右する
また、日常の中で「なぜこの広告は目に留まるのか」「この資料はなぜ見やすいのか」と考える習慣も、感覚を養うトレーニングになります。感性だけでなく、論理と目的を持ったデザインこそが、本質に近いものだと言えるでしょう。



