見てもらえてこそ始まる商談。展示会で目を引くブースデザインの考え方
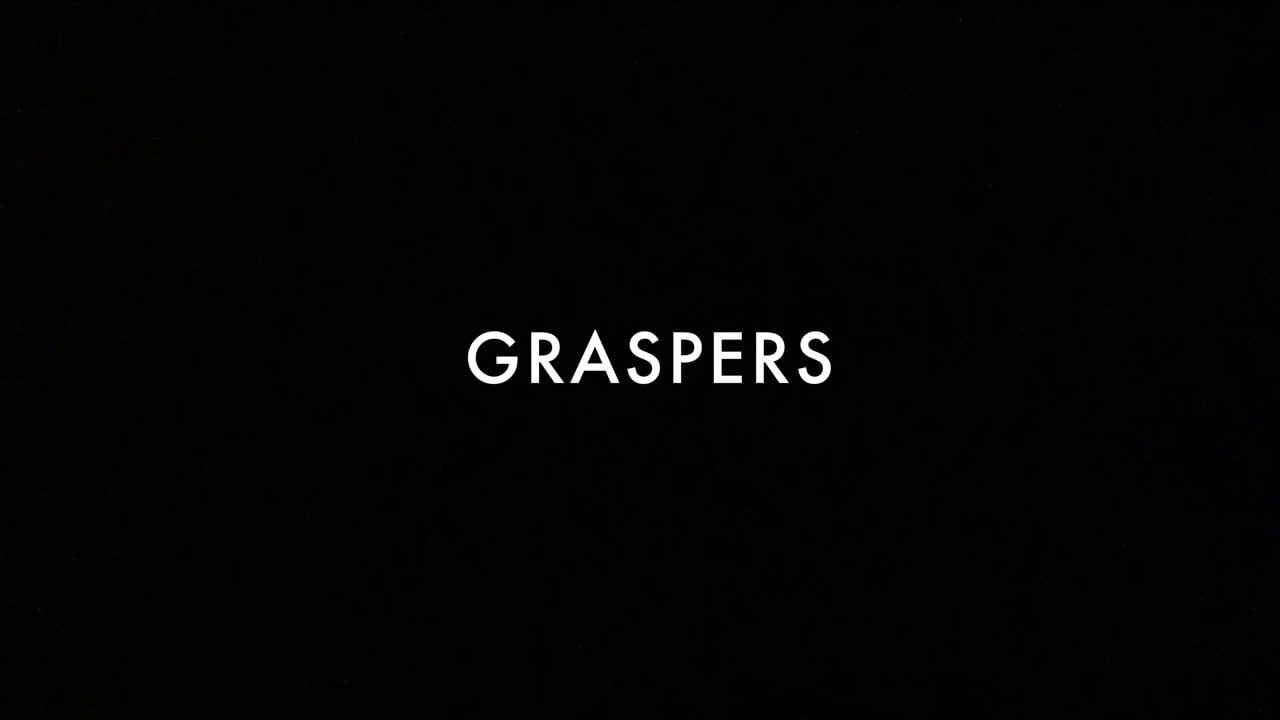
目次
展示会ブースの第一印象は「出会い」の入り口
展示会という場は、いわば一期一会の連続です。限られた時間の中で、初対面の来場者と出会い、自社のサービスや商品を知ってもらい、関心を持っていただく。その第一歩となるのがブースのデザインです。
出展社が何十社、あるいは百社以上にのぼる中で、どのようにして自社のブースに足を止めてもらうか。これは展示会で成果を出すための最初の課題です。
通路を歩く来場者の目に、ほんの一瞬でも「ん?」と引っかかる要素がなければ、ブースの前を素通りされてしまいます。言い換えれば、ブースのデザインは「無言の営業担当」のようなもの。まず見てもらえなければ、その後の商談にもつながりません。
人が集まるブースの共通点とは
来場者が自然と立ち寄るブースには、いくつかの共通点があります。
ひとつは、視認性の高さです。遠くから見ても何を扱っているのかが一目で伝わるキャッチコピーやロゴ、キービジュアルなどが効果的に配置されています。
もうひとつは、開放感。壁で囲まれた閉鎖的な空間よりも、出入りしやすく見通しの良いレイアウトの方が、立ち寄る心理的ハードルは下がります。
さらに、「気になる仕掛け」があることも大きな要素です。デモンストレーションを行っていたり、ちょっとした体験コーナーがあったりすると、自然と人が集まり、その様子に引き寄せられてさらに人が増えるという好循環が生まれます。
目的に応じてデザインコンセプトを明確に
ブースをつくるうえで最も大切なのは、「何のために出展するのか」という目的を明確にすることです。認知拡大、リード獲得、商談化、採用強化、テストマーケティングなど、目的によって最適なブースのあり方は変わります。
例えば、サービスの概要を広く知ってもらうことが目的なら、視覚的に分かりやすいビジュアルと短い説明文を前面に出す方が効果的です。一方、商談につなげたい場合は、落ち着いて話せるスペースや資料を置くカウンターの設置などが重視されます。
また、自社のブランドイメージや業種に合わせて、カラーや素材を選ぶことも重要です。IT系なら白やグレーを基調とした近未来的な印象、食品系なら木目調や温かみのある配色で親しみやすさを演出するなど、デザインにはコンセプトが必要です。
来場者の視線を意識した空間づくり
展示会場では、来場者は常に「歩きながら」情報を見ています。つまり、立ち止まる前に見える範囲、目線の高さ、歩くスピードなどを意識した設計が求められます。
一般的に、人の目は約1.5メートルから1.7メートルの高さに集中します。重要な情報やロゴは、その高さに配置することで目に留まりやすくなります。上部に吊るされたバナーや看板も効果的ですが、それはあくまで補助的な役割。実際に足を止めるきっかけになるのは、視線の高さにある情報です。
また、通路に面した部分にディスプレイや映像、商品サンプルなどを配置して、通行者の注意を引くことも有効です。すべてを詰め込むのではなく、「何を見せるか」「何を引き出しにして興味を持たせるか」を考えて設計しましょう。
デザイン以外の“動き”もブースの一部
ブースデザインは、什器やパネルだけではありません。スタッフの立ち位置、声かけのタイミング、配布する資料やノベルティなど、ブース内で起きているすべてが“演出”の一部です。
たとえば、来場者と目が合ったらすぐに挨拶をし、興味を持ってくれた方には丁寧に説明をする。あるいは、ブース内でさりげなく実演を続けていることで、通行人が思わず足を止める。そんな動きや雰囲気が、結果的にブースの印象につながります。
ブースのコンセプトと合わせて、スタッフの動きやトーンも事前にすり合わせておくことが、展示会の成功につながります。
まとめ:伝えたいことを、伝わる形で
展示会のブースデザインは、単なる装飾ではなく、自社の想いやサービスの魅力を伝えるための「伝達手段」です。どれだけすばらしい商品があっても、ブースが目に留まらなければ、知ってもらうことすらできません。
誰に、何を、どんな印象で届けたいのか。その答えがデザインの中に込められているとき、来場者はその想いを“感じ取る”ことができます。
展示会は、短時間で多くの人と接点を持てる貴重な機会です。その一瞬の出会いを最大限に活かすためにも、心を込めたブースづくりを意識してみてはいかがでしょうか。



