想いが届く紙モノをつくる。効果的なフライヤー制作の基本
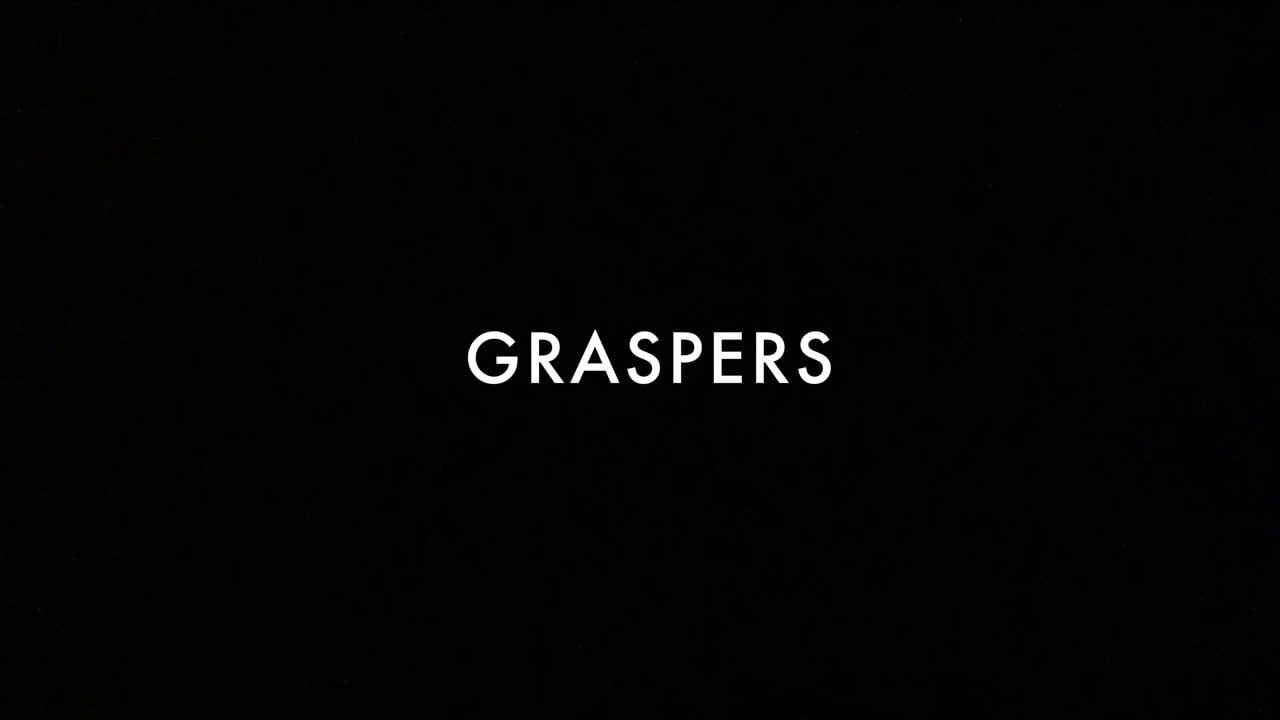
目次
フライヤーは今でも“効く”販促手段
デジタル時代の今、紙媒体はもう古いと考える方もいるかもしれません。しかし、フライヤー(いわゆる配布用の印刷物)は、手に取って見られるという点で、今なお根強い効果を発揮する販促ツールです。街頭や店頭、イベントなど、人と人が直接接するシーンでは、フライヤーを介した“物理的な接点”が信頼や記憶に残るきっかけになります。
特に地域密着型のビジネスやイベント、期間限定の告知などでは、Web広告だけでなく、フライヤーとの併用が効果的なケースも多く見られます。
チラシとの違いとは?フライヤーの定義
「チラシとどう違うの?」とよく聞かれることがあります。実は、厳密な定義に明確な線引きはありませんが、一般的には次のように使い分けられています。
フライヤーは、「広告」よりも「案内・告知」や「コンセプト紹介」などに使われることが多く、デザイン性が高めで、ブランドや世界観を伝える目的で制作される傾向があります。一方チラシは、スーパーの特売情報のように価格や商品情報を前面に出す実用的なツールです。
つまり、フライヤーは“情報を売る”というより、“価値や魅力を伝える”ツールとも言えるでしょう。
制作前に考えるべき3つの視点
フライヤーをつくる際は、いきなりデザインから始めるのではなく、「誰に」「何を」「どう伝えるか」の3つの軸を明確にすることが重要です。
まず、「誰に届けたいのか」を具体的に設定します。年齢層、性別、興味関心、地域性など、ターゲットが明確であるほど、言葉やデザインの方向性が定まります。
次に、「何を伝えたいか」を絞り込みます。サービスの特徴なのか、イベント開催の告知なのか、世界観の紹介なのか。一枚の紙で伝えられる情報には限りがあるため、欲張らずに伝えたいメッセージをひとつに絞ることがポイントです。
そして、「どう伝えるか」を考えます。文章とビジュアルのバランス、色使い、フォント選びなど、見た目の印象はそのまま“中身の印象”につながります。最初の数秒で惹きつけるための工夫が求められます。
伝わるフライヤーに欠かせない要素
反応が得られるフライヤーには、いくつか共通した要素があります。
まずはキャッチコピー。目を引く言葉、心に残る一文が冒頭にあるだけで、読み進めてもらえる可能性がぐんと上がります。
次に、伝えたい内容の整理。「どんなサービスか」「いつ・どこで行うか」「どんな人に向けてか」といった基本情報を、誰にでも分かるように構成します。
そしてビジュアル。写真やイラストの質は、ブランドの信頼性や雰囲気を大きく左右します。手にした瞬間、「このお店、よさそう」「行ってみたい」と思わせることができれば成功です。
最後に、アクションの導線も忘れずに。「詳しくはWebへ」「予約はこちらから」など、次の行動につなげる案内を明確にしておきましょう。
成果を上げるための工夫と配布のコツ
どれだけ良いフライヤーをつくっても、届け方を誤ると効果は半減します。ターゲットがよく集まる場所や時間帯を見極めて配布すること、設置する店舗や施設との相性を考えることが重要です。
たとえば、親子向けイベントの案内であれば、子育て支援施設や小児科、カフェなどへの設置が効果的です。あるスタートアップ企業では、自社のフライヤーを商店街の3店舗に置いてもらった結果、1週間でWebのアクセス数が2倍になったという事例もあります。
また、SNSやWebサイトと連動したデザインにすることで、「紙からデジタル」へとつながる動線もつくれます。
最後に:フライヤーは“伝え方”次第で強力な武器になる
全国の経営者やスタートアップ事業者の皆様へ。フライヤーは今も、丁寧に想いを伝えることのできる有効な手段です。デジタルでは届きにくい層へ、あるいは空間を彩るブランドの一部として。紙という媒体が持つあたたかさや確かさを活かしながら、“伝える”ではなく“伝わる”制作を、ぜひ意識してみてください。



