ホームページ制作の費用相場を完全解説【2025年版】

ホームページ制作を検討するとき、もっとも気になるのは「費用はいくらかかるのか」という点ではないでしょうか。実際には依頼先やサイトの規模、デザインレベルや追加機能によって制作費用は大きく変動します。
フリーランスに依頼すれば10万円台で収まることもあれば、大手制作会社に依頼すれば数百万円以上になるケースも珍しくありません。さらに制作後にはサーバーやドメイン、保守管理などの運用費用も継続的に発生します。
この記事では、2025年最新のホームページ制作費用相場を徹底的に解説します。依頼先別・目的別の料金目安、制作費用の内訳、運用コスト、さらには費用を賢く抑える実践的な方法まで幅広く紹介します。これからホームページ制作を考えている方は、ぜひ参考にしてください。
費用を正しく見極めるには、初期費用だけでなく3年程度の総保有コストで比較することが大切です。サーバー・保守・更新制作・広告やSEOなど運用費まで含めて、ホームページ制作の投資対効果(KPI達成コスト)を試算しましょう。見積比較では「内訳 × 想定工数 × 体制 × 成果仮説」を軸に、修正回数・定例MTG頻度・納期遅延時の対応・著作権とデータ納品範囲・公開後SLA(応答/復旧目安)を文書化しておくと安心です。要件は“必須/任意/将来”に分けて優先度を明示し、ミニマム構成で公開→データを見ながら拡張する流れを前提にすると、無駄なコストを抑えつつ成果を出しやすいホームページ制作になります。

目次
ホームページ制作を始める前に知っておくべき基本知識
ホームページを作る前に大切なのは「なぜ作るのか」を明確にすることです。会社案内や商品販売、採用強化など目的によって必要なページや機能は大きく変わります。また、デザインのこだわり方やサイトの規模によって費用も変動するため、事前に方向性を定めることがコスト管理にもつながります。ここでは制作前に知っておきたい基本的な考え方を整理します。
ホームページの目的と役割を明確にする
まず重要なのは、「何のために作るのか」という目的をはっきりさせることです。会社案内を目的とするなら信頼性を伝える設計が必要です。採用サイトであれば求職者に魅力を伝えるコンテンツが欠かせません。目的が曖昧なまま進めると、不要な機能にコストをかけてしまうリスクがあります。逆に必要な機能を盛り込めなければ、期待する成果を得られません。
必要な機能とデザインレベルを決める
費用を大きく左右する要素の一つが、機能とデザインのレベルです。最低限のデザインで良いのか、ブランド戦略を意識した高品質なデザインが必要なのかを考える必要があります。例えばシンプルなコーポレートサイトなら30万円前後で済みますが、予約機能や会員機能を追加すると100万円を超えることもあります。
制作費用を左右する3つの重要ポイント
- 依頼先の規模とスキル(フリーランスか制作会社か)
- サイトの規模とページ数(ページが増えるほど費用も増加)
- 追加機能やコンテンツ制作の有無(撮影やライティングは別途費用)
制作費用を検討するときの隠れた落とし穴
ホームページ制作の見積もりでは、一見すると明確に見える金額でも、実際には「含まれていない費用」が潜んでいることが少なくありません。例えば、サーバー契約代行費用やアクセス解析ツールの導入費用、ライティングや撮影といったコンテンツ制作部分が別料金となっているケースは多いです。また、CMSのカスタマイズが想定以上に必要になると、当初の見積もりから数十万円単位で膨らむこともあります。費用を抑えたいなら、最初の段階で“何が含まれていて、何が別途なのか”を必ず確認し、見積書の内訳を詳細にチェックすることが不可欠です。
ホームページ制作の費用感を決める「人件費」の考え方
制作会社の見積もりの大部分は工数=人件費です。ディレクター、デザイナー、フロントエンドエンジニア、バックエンドエンジニア、ライター、カメラマンといった専門職が関わるほど、費用は増加します。逆にいえば、担当人数を絞れば費用は抑えられますが、その分クオリティや納期のリスクが高まります。費用を適正化するには、どこまで自社で準備し、どの部分を外注するかを整理することが大切です。社内に担当者を立てて文章や写真をある程度用意しておけば、制作会社の工数が減り、その分ホームページ制作の総額も下げられる可能性があります。
追加機能と拡張性をどう考えるか
初期費用だけを見て依頼すると、将来的に「もっとこうしたい」というニーズが出たときに高額な追加費用が発生することがあります。例えば、最初は会社案内ページだけだったものの、半年後に採用サイトを追加したい、1年後にEC機能を付けたいとなれば、設計をやり直す必要が出ることもあります。そのため、ホームページ制作を始める際には、最低限でも今後1〜2年の事業計画を踏まえて必要な機能や拡張性を検討しておくことが重要です。短期的なコスト削減だけを重視すると、結果的に高くつくケースも少なくありません。
事前に用意しておくと見積精度が上がるチェックリスト
ホームページ制作では、依頼側の準備次第で費用ブレが大きく減ります。
(1) 目的/KPI(問い合わせ月◯件・採用応募◯件)
(2) 主要ターゲット像と検索キーワード
(3) 必須ページ一覧(優先度/公開可否)
(4) 必須機能(問い合わせ/予約/会員/決済)
(5) 原稿・写真の用意範囲
(6) 想定更新頻度と運用体制
(7) 参考サイト3つ(好き/嫌いの理由)
(8) 期日と審査フロー
を事前に共有しましょう。これらが揃うと、見積の内訳と工数が具体化し、不要なバッファ費用が削減されます。さらに「最小構成で先行公開→計測→改善」という流れを合意しておけば、投資のタイミングを分散でき、ホームページ制作の総コスト最適化にも直結します。

【早見表】ホームページ制作費用の相場一覧
制作費用は依頼する相手やサイトの規模、目的によって幅広く変動します。フリーランスと制作会社、大手企業とでどれくらいの違いがあるのか、またコーポレートサイトやECサイトなど目的ごとの相場も異なります。この章では、一般的な相場を早見表形式でまとめ、予算感を持つための参考にしていただける内容を紹介します。
依頼先別の料金相場
■フリーランスの相場(10万円~100万円)
フリーランスは費用を抑えたい場合の有力な選択肢です。小規模サイトなら10万円~30万円程度で依頼可能です。ただしサポート体制や納期リスクには注意が必要です。
■中小制作会社の相場(30万円~300万円)
中小規模の制作会社は費用と品質のバランスが良い点が魅力です。30万円前後の小規模サイトから、200万円以上のECサイトまで幅広く対応します。
■大手制作会社の相場(100万円~)
大手は高度な提案力や実績を持ち、ブランド戦略を含めたサイト制作が可能です。費用は最低100万円からで、500万円を超える案件もあります。
| 依頼先 | 費用相場 | 特徴 |
|---|---|---|
| フリーランス | 10万円~100万円 | 費用が安い。小規模向き。ただしサポートに不安あり。 |
| 中小制作会社 | 30万円~300万円 | 品質と価格のバランスが良い。幅広い規模に対応。 |
| 大手制作会社 | 100万円~500万円以上 | 提案力と実績が豊富。ブランド戦略や大規模案件向き。 |
サイト規模別の料金相場
ホームページは作る規模感で費用が異なります。必要なことは、自社の規模・表現したい内容に見合ったホームページを制作することです。自他共に違和感のない、正しい規模感のホームページを選択するようにしましょう。ページ数は“今の情報量”ではなく、1年後の運用計画から逆算します。最初は必要最低限で公開し、カテゴリー構成とURL設計だけ先に用意すれば、後からの増築が痛みなく行えます。無理に大規模にせず、更新体制に見合った規模が結果的に安くて強いサイトになります。
| サイト規模 | ページ数の目安 | 費用相場 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 小規模サイト | 10ページ以内 | 10万円~50万円 | 会社概要やサービス紹介など最小限。 |
| 中規模サイト | 30ページ以内 | 50万円~150万円 | 採用ページやブログ機能を追加。 |
| 大規模サイト | 50ページ以上 | 150万円~500万円以上 | オウンドメディアや大規模ECサイト。 |
目的別の料金相場
大手は高度な提案力や実績を持ち、ブランド戦略を含めたサイト制作が可能です。費用は最低100万円からで、500万円を超える案件もあります。LPは広告運用ありきで設計すると費用が活きます。採用サイトはカルチャーや働く人の顔が見えることが重要で、写真と原稿に投資価値があります。ECサイトは在庫・配送・返品の運用フローが売上を左右するため、システム費だけでなく運営コストも同時に見積もるのがポイントです。ホームページは目的を明確にして制作することが大事です。
| サイトの種類 | 費用相場 | 特徴 |
|---|---|---|
| コーポレートサイト | 30万円~100万円 | 会社紹介や信頼性の向上に最適。 |
| ECサイト | 100万円~300万円 | 商品数やカート機能で費用が変動。 |
| ランディングページ | 10万円~50万円 | 広告用の1ページ完結型サイト。 |
| 採用サイト | 50万円~150万円 | 写真撮影や採用情報を充実。 |
| オウンドメディア | 100万円~300万円以上 | 記事更新やSEO対策を前提に設計。 |
フリーランスは短距離走に強く、制作会社は駅伝型の継続運用に強い傾向があります。自社が欲しいのは「早さ」か「体制」かを先に決めてから見積りを取りましょう。また、窓口の人が制作にどれだけ関わるかで実行速度は変わります。営業専任窓口だけの体制より、ディレクターが直接窓口に立つ体制の方が、意思疎通のロスが少なく手戻りも減ります。

ホームページ制作料金の内訳を徹底解説
見積もりに含まれる費用は「何にどれくらいかかるのか」が分かりにくいものです。ディレクションやデザイン、コーディングといった基本費用に加え、システム開発やSEO対策などのオプション費用も発生します。ここでは費用の内訳を丁寧に分解し、制作料金がどう決まっているのかを具体的に説明します。
基本制作費用の内訳
ディレクション費(企画・進行管理)
サイト全体の設計と進行管理のための費用です。10万円~30万円程度が一般的です。ホームページ制作では、企画段階での方針決めやスケジュール管理が完成度を左右します。目的やターゲットを誤らないために必要な費用であり、打ち合わせや提案内容が多いほどコストは上がります。見積りでは要件定義・進行管理・品質管理・検収対応のどこまで含むかを明記してもらいましょう。定例MTGの回数と時間、チャットの応答SLA、想定修正回数も曖昧だと後日追加費用になりがちです。
デザイン費(ビジュアル設計)
見た目の印象を決める重要な工程で、20万円~100万円程度が目安です。ブランドイメージを重視する場合はさらに高額になります。ブランドイメージを重視する場合はさらに高額になります。ホームページ制作におけるデザインは第一印象を左右し、ユーザーの滞在時間や信頼感に直結します。テンプレートを利用すれば安く抑えられますが、オリジナルデザインは差別化に効果的です。「TOP+下層共通」のテンプレか、「主要テンプレ×複数」かで費用が大きく変わります。また、ワイヤフレーム→デザインカンプ→モックの各ステップで修正回数を決めておくと、トラブル防止になります。
コーディング費(実装作業)
デザインをWebに落とし込む作業で、ページ数に比例して費用が上がります。ホームページ制作では、正確なコーディングが表示速度やSEO評価にもつながります。レスポンシブ対応や動きのあるアニメーションを取り入れる場合には追加費用が発生することもあります。価格に差が出るのは、再利用可能なコンポーネント設計の有無です。後からページ追加する前提なら、ヘッダー/カード/CTA/FAQなどのパーツを最初に設計しておくと拡張コストが下がります。アクセシビリティ(代替テキスト、コントラスト比、キーボード操作)対応は長期のSEO/UXにも効きます。
コンテンツ制作費(テキスト・画像)
原稿作成や写真撮影を外注する場合は10万円~50万円程度かかります。高品質なコンテンツはSEO対策にも欠かせないため、ホームページ制作では重要な投資項目です。自社で素材を用意できれば費用を抑えられますが、プロに依頼することでより信頼性の高いサイトに仕上がります。“社内で下書き→プロが磨く”二段構えにすると、コストを抑えつつ専門性・一次情報を活かせます。写真は被写体・場所手配・レタッチの範囲で費用が上下します。撮影リスト(シーン/人物/用途)を先に作れば、撮り漏れが減り再撮影のリスクを抑えられます。
オプション費用の内訳
システム開発費(機能実装)
予約システムや会員機能などの追加で50万円以上になることもあります。予約システムや会員機能などの追加で50万円以上になることもあります。ホームページ制作に機能を追加する場合、汎用のプラグインで対応できることもありますが、独自システムを構築する場合は高額になる傾向があります。まずは既成プラグインで代替できるか確認しましょう。独自開発は“仕様変更=費用増”のインパクトが大きいので、MVP(最小機能)で先に公開し、利用データを見て段階実装が安全です。
マーケティング設計費
広告運用やアクセス解析を含める場合は10万円~30万円程度。ホームページ制作を成功させるためには、ただ公開するだけでなく、集客から成果につなげる導線設計が不可欠です。初期段階からマーケティング設計を組み込むことで、費用対効果を高められます。計測タグの設置/イベント設計/コンバージョン定義が入っているかは必ず確認。運用前提なら、運用レポートの頻度とKPI(CV数、CVR、CPA、ROAS)を文章で合意しておきます。
SEO対策費
検索上位を狙う施策に10万円~100万円程度かかります。ホームページ制作の段階でSEOを意識することは、後々の集客力を左右します。内部構造の最適化や記事設計を含め、長期的に検索流入を確保するためには欠かせない費用です。内部施策(情報設計/内部リンク/スキーマ)と記事SEO(KW調査/記事設計/校正)は費目が別になることがあります。短期で順位が動かないことも多いので、四半期KPIで評価する運用にしておくと、社内説明がスムーズです。
制作費用を抑えるための実践的チェックリスト
(1)自社でできること(文章草案・写真素材)を明確にする
(2)1年後・3年後に必要になる機能を想定しておく
(3)修正回数や打ち合わせ頻度を契約前に決める
(4)内訳の「どこまでが含まれるか」を細かく確認する
(5)運用コスト(サーバー・ドメイン・保守)を初期費用に含めて考える
これらを実行するだけで、無駄なコストの発生を大幅に減らせます。見積もりを比較する際は、金額の安さだけでなく「必要な内容が全て含まれているか」を基準にすることで、結果的に安心できるパートナー選びにつながります。
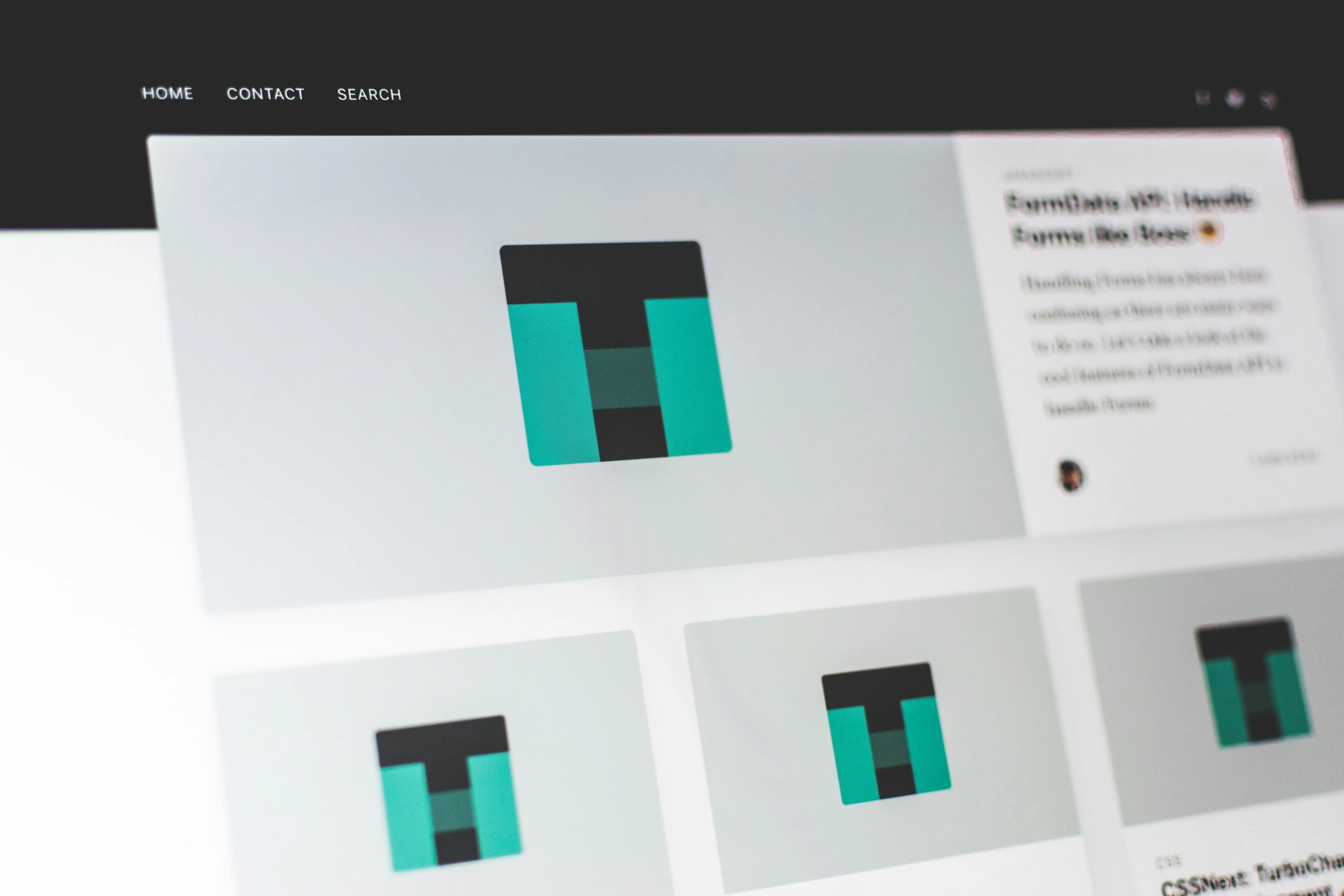
なぜ制作会社によって料金が大きく異なるのか
同じホームページ制作であっても、制作会社ごとに提示される金額が大きく違うことがあります。その背景には、会社の実績や専門性、デザインやマーケティングへのこだわり、サポート体制の厚さなど多くの要因があります。ここでは料金差を生む要素を整理し、なぜ見積もりが幅広くなるのかを解説します。
価格差を生む9つの要因
まず、もっとも分かりやすい違いは制作実績や専門性の差です。経験豊富な会社は高度な提案ができるため、費用は高くなりがちです。また、デザインを一からオーダーメイドで作るのか、既存のテンプレートを活用するのかによっても価格は変わります。オリジナル性を重視すればするほどコストは上がります。さらに、制作に必要な文章作成や写真撮影を含めるかどうかも大きな分かれ目になります。素材をすべて自社で用意できる場合は費用を抑えられますが、外注すると追加費用がかかります。
そのほかに、マーケティング設計をどこまで深く行うかも重要です。単にサイトを作るだけでなく、集客戦略やSEO設計を含めると費用は上がります。また、サポート体制の手厚さによっても差が生まれます。納品後の保守や更新を任せられる会社は安心ですが、その分費用が高めです。加えて、CMS(WordPressなど)の導入やカスタマイズを行うかどうかも影響します。標準機能で十分な場合は安価ですが、大幅なカスタマイズを加えるとコストが増します。
デザインの独自性も価格に直結します。テンプレートを基にしたデザインなら低価格で済みますが、ブランドを意識したオリジナルデザインは費用がかかります。そして、納期の短さも大きなポイントです。短期間で仕上げる場合、追加の人員や工数が必要になるため価格は高くなります。最後に、契約形態の違いも見逃せません。成果物の納品を前提とした「請負契約」と、期間や工数に応じて支払う「準委任契約」とでは、費用の算出方法が変わり、結果的に価格差につながります。
フリーランスvs制作会社のメリット・デメリット
フリーランスに依頼する場合
メリットは費用が安く柔軟な対応が可能な点。デメリットはサポート不足や納期リスクです。メリットは費用が安く柔軟な対応が可能な点です。小規模なホームページ制作では、10万円前後から依頼できることもあります。デメリットは、制作や運用を一人で担うため、納期遅延やトラブル対応に不安が残ることです。
制作会社に依頼する場合
メリットは体制が整っており、デザイン・開発・SEO対策まで一貫して任せられる安心感がある点です。ホームページ制作を本格的に進めたい場合や中長期的な運用を見据えた企業には適しています。デメリットはフリーランスに比べて費用が高く、数十万円から数百万円になるケースもある点です。
結局どちらに依頼すべきか?判断の目安
フリーランスと制作会社、どちらを選ぶべきか迷う方は多いでしょう。判断のポイントは「ホームページ制作後の運用をどこまで自社で担えるか」です。もし社内に担当者がいてSEOや更新作業を自力で進められるなら、フリーランスに依頼して初期費用を抑える選択も現実的です。逆に、公開後も継続的に改善や更新を行いたい場合や、リスクを最小限にしたい場合は制作会社が安心です。単に費用の安さだけでなく、自社のリソースや体制に合った依頼先を選ぶことが、長期的な成功への近道になります。

ホームページの運用・維持費用も忘れずに
ホームページは完成して終わりではなく、公開後にも維持費や運用コストがかかります。サーバーやドメインといった必須費用に加え、セキュリティ強化のためのSSL証明書費用、定期的な保守管理費や更新費用も必要です。この章では制作後に見落とされがちなランニングコストを整理し、長期的な予算設計に役立てていただける内容を紹介します。
必須の維持費用
サーバー・ドメイン費用
年間1万円~3万円程度が一般的です。サーバーはサイトの表示速度や安定性に直結するため、ホームページ制作後の信頼性を考えると安さだけで選ぶのは危険です。ドメインはブランドの資産にもなるため、長期的に維持管理していくことが大切です。更新を忘れるとサイトが表示されなくなるリスクもあるため注意しましょう。
SSL証明書費用
セキュリティ強化のために年間1万円前後が必要です。常時SSL化はGoogleの推奨項目でもあり、ホームページ制作段階から導入しておくとSEO効果にもつながります。特に問い合わせフォームやEC機能を備えたサイトでは、利用者の安心感を確保するために欠かせない要素です。
運用・改善費用
保守管理費用
月額5,000円~3万円程度。障害対応やセキュリティアップデートが含まれます。ホームページ制作は完成して終わりではなく、定期的な更新と管理が安定運用には不可欠です。万一の不具合やサーバートラブルにも迅速に対応できる体制を整えておくと安心です。
コンテンツ更新費用
記事更新や写真追加を外注する場合、1記事1万円~5万円程度。定期的な更新はSEO評価を高め、ホームページ制作後の成果を継続的に伸ばす鍵になります。特に採用情報や新商品紹介のように鮮度が重要なページは、定期更新で信頼感を高める効果があります。
継続的なSEO対策費用
検索順位を維持するために月額3万円~10万円程度が目安です。競合の多い業界では、ホームページ制作後も継続的にSEO施策を行わなければ検索流入が減少する可能性があります。専門的な分析や改善を取り入れることで、長期的に安定した集客基盤を築けます。

制作費用を賢く抑える6つの実践的方法
ホームページ制作は工夫次第で費用を抑えることが可能です。写真や原稿を自社で準備する、段階的にサイトを構築する、複数社から見積もりを取るなど、実践できる方法はいくつもあります。ここでは無理のない範囲でコストを抑えながら、必要な品質を確保するためのポイントを6つに分けて紹介します。
自社でできる準備と対応
1.素材(写真・原稿)の自社準備
自社で用意すれば外注コストを削減できます。写真や文章は社内でしか表現できない強みを打ち出せる部分でもあり、ホームページ制作の個性を高める重要な要素です。あらかじめ素材を揃えておくと制作スケジュールもスムーズになり、納期短縮にもつながります。
2.段階的なサイト構築も検討
最初は小規模で始め、段階的に拡張していく方法も有効です。限られた予算でホームページ制作を始めたい企業にとって、段階的な構築は無理のない投資計画になります。将来的な事業の成長や方向転換に合わせて柔軟に対応できる点も大きなメリットです。
発注時の工夫とコツ
3.テンプレート活用による費用削減
既存のデザインを活用すれば工数が減り費用も抑えられます。テンプレートを利用したホームページ制作は短納期で公開できるため、スピード重視のプロジェクトにも適しています。デザインの自由度は制限されますが、初期段階で必要十分なサイトを持つことが可能です。
4.複数社からの見積もり比較
最低でも3社から見積もりを取り、相場を把握するのが基本です。同じ条件でもホームページ制作会社ごとに費用差が出るため、複数の見積もりを比較することで最適な依頼先を見つけやすくなります。金額だけでなくサービス内容やサポート範囲も確認することが大切です。
5.CMSの導入と自社更新体制
WordPressなどを導入すれば、自社で更新でき長期的なコストを削減できます。CMSを活用したホームページ制作は、専門知識がなくても更新が可能になるため、運用負担を大きく減らせます。定期的な情報発信を自社で行うことで、SEO強化にもつながります。
6.作業範囲と料金体系の明確化
契約前にどこまでが費用に含まれるのかを明確に確認することが重要です。ホームページ制作では、要件が追加されると想定外のコストが発生するケースも多いため、見積もり段階で詳細に確認しておく必要があります。透明性のある契約はトラブル防止と信頼関係の構築にもつながります。

東海((岐阜・愛知・名古屋・三重))でホームページ制作会社をお探しならグラスパーズへ
東海((岐阜・愛知・名古屋・三重))エリアでホームページ制作を検討しているなら、地域に根ざした制作会社を選ぶことをおすすめします。当社グラスパーズはWeb制作・戦略支援・SEO対策をワンストップで提供し、地元企業に寄り添ったサポートを行っています。最新のマーケティング手法と地域密着型の対応を両立しているのが強みです。

まとめ
ホームページ制作の費用は、依頼先・規模・目的によって大きく変動します。小規模なら10万円台から始められ、大規模なら500万円以上になることもあります。制作費用だけでなく、運用・維持費用も含めた総合的なコスト設計を意識することが大切です。目的に合わせて適切な制作範囲を設定すれば、無駄なコストを削減できます。さらに、制作の際にはデザイン性だけでなく、更新のしやすさや集客効果、SEO対策なども考慮することで長期的な成果につながります。公開後の運用体制を事前に決めておくことも重要で、定期的な情報発信やアクセス解析を行うことでホームページの効果を最大化できます。制作会社を選ぶ際には、料金の安さや見た目の良さだけでなく、パートナーとして信頼できるかどうかを確認しましょう。実績やサポート体制、将来的な拡張への対応力などを踏まえて比較することが、失敗を防ぐポイントです。
ホームページ制作を検討している方は、当社へ是非ご相談ください。成果につながるホームページを実現するために、最適なパートナー像を目指しています。



