サイトリニューアルの失敗事例12選と原因を解説
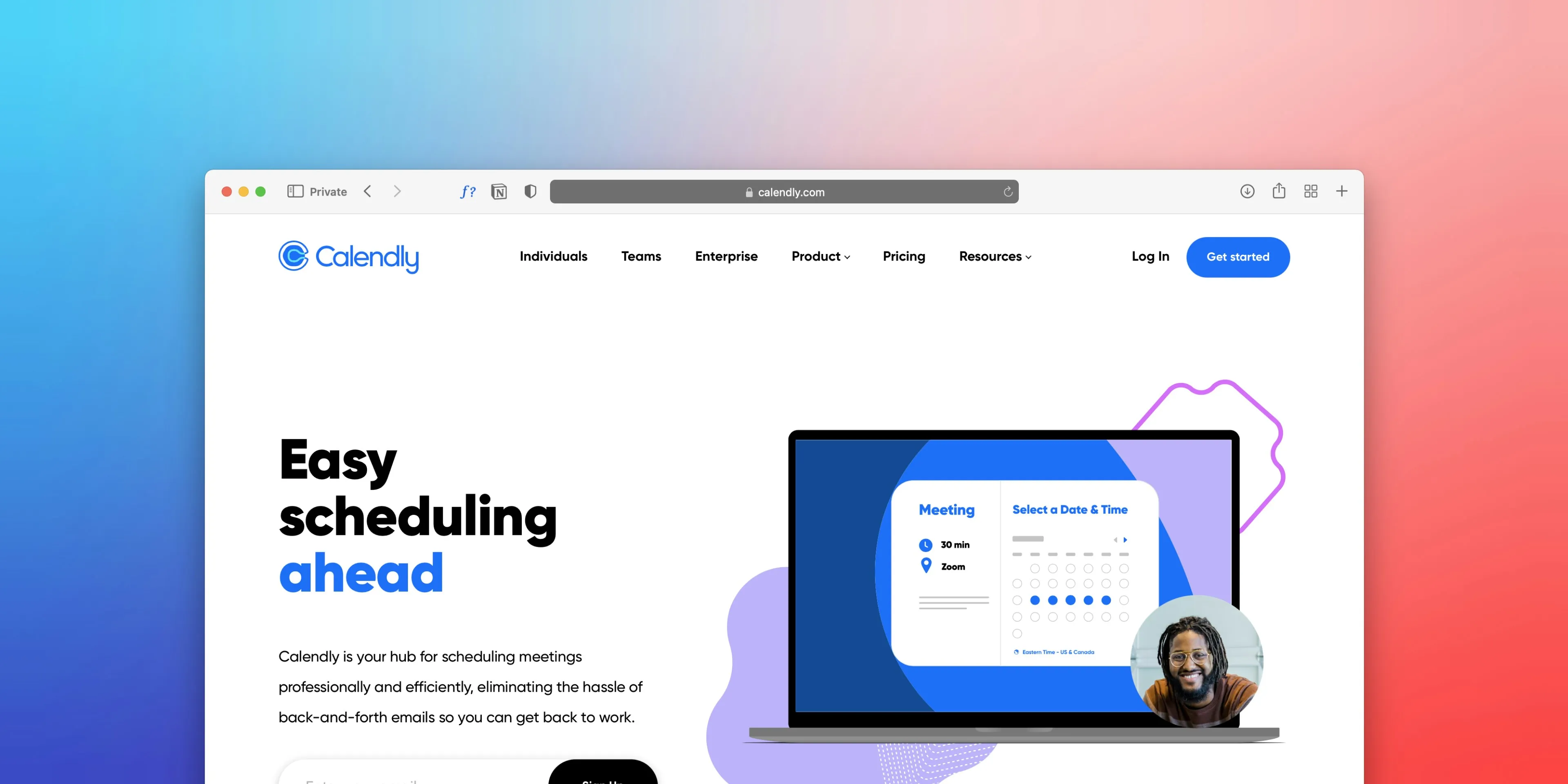
企業や店舗のホームページを新しく作り変える「サイトリニューアル」。
しかし、見た目が良くなったのに問い合わせが減った、アクセスが半分以下になった、検索順位が落ちた――。
こうしたリニューアル後の失敗は、実は少なくありません。
サイトを新しくすること自体は前向きな投資ですが、設計や進行の仕方を誤ると、これまで積み上げてきた信頼やSEO評価を失うこともあります。特に、URL構造の変更やコンテンツ削除、内部リンクの見直し不足などが原因で、検索エンジンからの評価がリセットされてしまうケースは多く見られます。また、デザイン重視のあまりユーザビリティ(使いやすさ)が損なわれたり、スマートフォン対応が不十分で離脱率が上がることも珍しくありません。リニューアルは「見た目を変える作業」ではなく、「成果を高めるための戦略的な再設計」であることを理解することが重要です。
さらに、リニューアルに関わる社内外のコミュニケーション不足も失敗の要因になりがちです。経営者・担当者・制作会社の間で目的やターゲット像が共有されていないと、方向性のズレが生まれ、結果として「誰のためのサイトか」が不明確になります。ユーザー視点を置き去りにしたままデザインや機能を優先してしまうと、せっかくの投資が逆効果になることも。リニューアルの成功には、データ分析や顧客行動の理解、そして長期的な運用計画が欠かせません。加えて、リリース後の検証と改善を怠らない継続的なPDCAサイクルも成果を伸ばす鍵となります。
本記事では、サイトリニューアルでよくある失敗事例12選とその原因、そして再発防止のための具体策を徹底的に解説します。リニューアルを検討している方、あるいはすでに進行中の担当者にとって、失敗を未然に防ぐための実践的なヒントをお届けします。
目次
サイトリニューアルでよくある失敗事例
アクセス数・問い合わせ数が減少した
サイトリニューアル後に最も多いトラブルが、アクセス数の急激な減少です。デザインを刷新し、コンテンツを整理したのにもかかわらず、流入が激減し、問い合わせも減少する。原因は多くの場合、SEOとリダイレクト設定の不備です。
古いURLを削除したまま新しい構造を導入すると、Googleが旧ページの評価を引き継げません。特に「301リダイレクト」が設定されていない場合、旧ページのリンク価値が途絶え、検索順位の下落につながります。
また、Googleアナリティクスやサーチコンソールのトラッキング設定をリニューアル時に失念するケースもあります。これにより実際のアクセスは維持されていても、データが記録されず“ゼロ”に見えてしまうことがあります。
- ポイント:
- ・URL変更時は必ず301リダイレクトを設定
- ・旧URLと新URLのマッピング表を作成
- ・Googleツールの再設定を忘れない
これだけで多くのアクセス減少トラブルは防げます。
検索順位が大幅に下落した
検索順位が落ちると、企業サイトにとって致命的な打撃になります。
特にBtoBの問い合わせ依存型ビジネスでは、自然検索からの流入が売上の大半を占めている場合もあります。
順位下落の主な原因は次の通りです。
- 1.titleタグ・meta descriptionの変更
- 2.内部リンク構造の崩壊
- 3.コンテンツボリュームの削減
たとえば、以前上位を取っていたページがリニューアル後に別URLへ移動したにもかかわらず、内容が簡略化されていると、Googleは「このページは前より情報が少ない」と判断し、順位を下げます。
また、リニューアルを機にmetaタグを一括自動生成に切り替えるケースもありますが、テンプレートでの一律設定は重複title・descriptionを生み、SEO評価を下げる結果につながります。
ユーザビリティが低下した
リニューアルは見た目を良くする作業ではなく、使いやすさを改善する行為であるべきです。しかし実際には、デザインを重視するあまりユーザビリティを損なうことがよくあります。たとえば、
- ・スマホで文字が小さくて読めない
- ・メニューがハンバーガーアイコンに隠れて直感的に操作できない
- ・フォームの入力項目が増えて送信完了率が下がる
こうした変更は、サイト訪問者の行動率を大きく下げます。Googleはモバイルユーザー体験を重視しているため、UX(ユーザーエクスペリエンス)の低下はSEO順位にも影響します。
対策:モバイル視点での導線テスト、ヒートマップ分析、フォーム改善。「おしゃれ」よりも「使いやすい」を優先することが重要です。
デザインだけ変わって成果が出ない
「見た目は綺麗になったのに問い合わせが増えない」というのは典型的な失敗です。リニューアルの目的が「印象を良くする」だけに留まっていると、コンバージョン導線が最適化されません。
成果を生むリニューアルには、明確なコンバージョンポイント設計が欠かせません。CTA(ボタンやフォームへの誘導)は、色・配置・テキストまで心理的に設計する必要があります。
また、導線の一貫性が重要です。トップページからサービスページ、問い合わせフォームへと自然に導く「シナリオ設計」が成果を左右します。
運用の手間が増えてしまった
リニューアル後に「更新しにくくなった」「社内で操作できない」という声も多く聞かれます。CMS(WordPressなど)を導入したにもかかわらず、運用者が扱えない構造になっているケースです。
更新しやすさを優先するなら、テンプレートの統一化と管理権限の設計が必要です。また、デザイン要素を変更するたびにコーディングが必要になるような構成は、長期運用に不向きです。
予算オーバーで完成度が低い
リニューアルで最も避けたいのが、途中で予算が尽きて中途半端なまま公開することです。見積もり段階で要件を整理していないと、開発途中で仕様追加が重なり、最終的にコストが倍増します。対策としては、
- ・要件定義書を作成する
- ・フェーズ分割(第1期:公開/第2期:機能追加)を行う
- ・制作会社との契約に「追加費用条件」を明示する
これらを徹底すれば、コストトラブルを防ぎつつ品質を確保できます。
CVR(コンバージョン率)が下がった
アクセス数は維持しているのに成果が減る――。
これは、リニューアルでフォーム構造やCTA配置を変えた際に発生します。
フォーム項目を増やす・ボタン文言を変えるなどの微妙な変更が、コンバージョンに影響します。また、フォーム完了後のサンクスページを削除したことで、リマーケティングタグが発火しなくなり分析が途絶えるケースもあります。
重要なのは「データの連続性」です。リニューアル前後で計測設定が一致していなければ、効果を正確に比較できません。
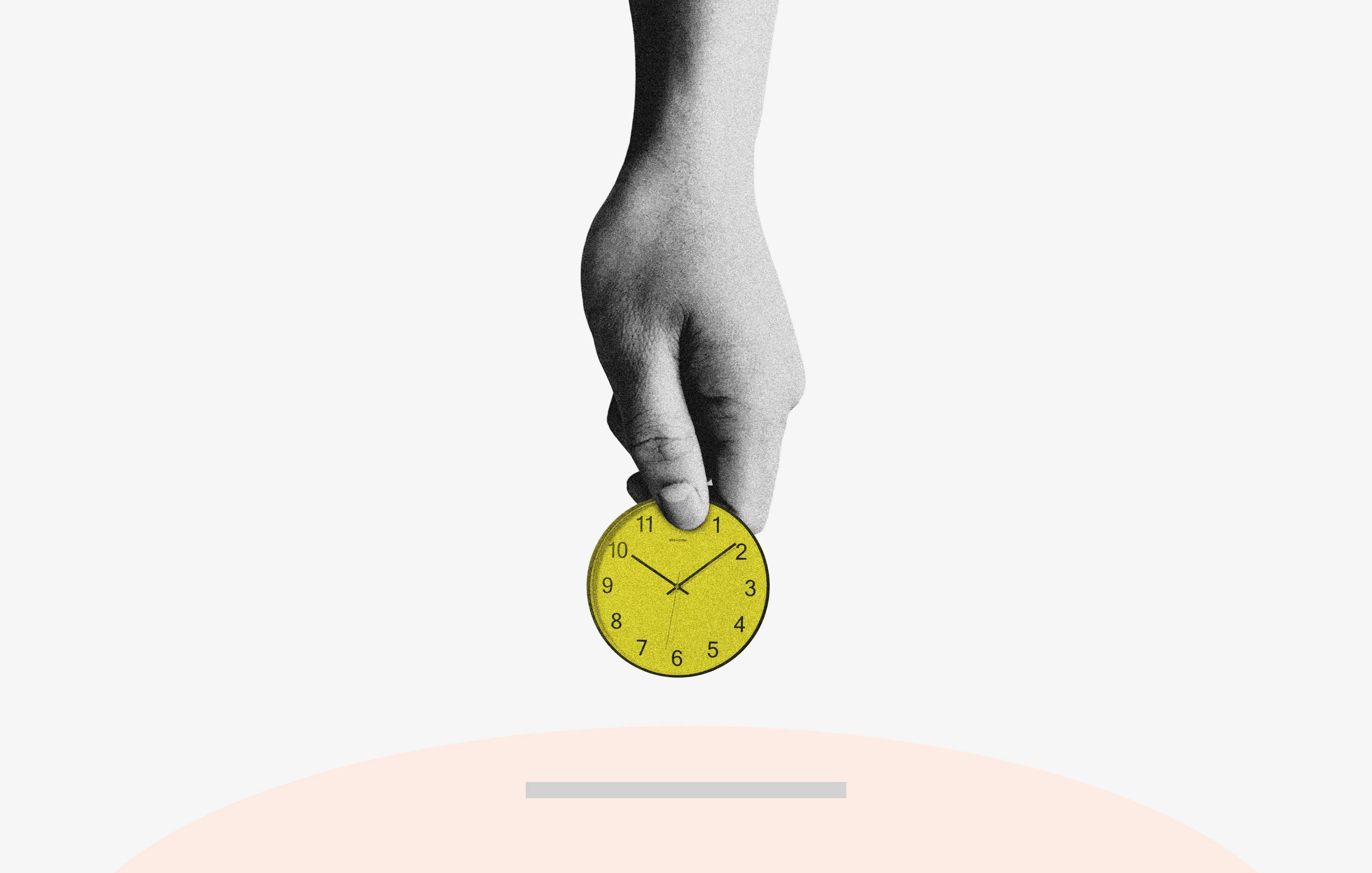
リニューアル失敗の主な原因
ここまでの事例を踏まえると、サイトリニューアルの失敗には「計画」「分析」「設計」「運用」の4段階に共通の欠点があることがわかります。それぞれの段階で起こりやすいミスを整理し、どう防ぐかを解説します。
目的が曖昧なまま着手した
「なんとなく」のリニューアル
「古いから変えたい」「他社が新しくしていたから」といった曖昧な理由でリニューアルを始めると、方向性が定まりません。制作会社は具体的なゴールが提示されないと、判断基準を持てず、結果として“見た目だけの刷新”になりがちです。
目標設定の不在
目標は「問い合わせ数を1.5倍に」「求人応募数を月10件に」など、定量的に設定することが重要です。目標が明確であれば、判断基準も明確になり、デザイン・SEO・導線が一貫性を持ちます。
課題分析が不十分だった
サイトリニューアルで失敗する原因の中でも特に多いのが、事前分析の浅さです。既存サイトの問題点をデータで把握せずに進めると、リニューアル後も同じ課題を繰り返します。現行サイトを分析する際は、以下の項目を必ずチェックします。
- ・ページごとのアクセス数・滞在時間・離脱率
- ・コンバージョン導線の流れと離脱点
- ・各デバイス(PC・スマホ・タブレット)での閲覧率
- ・検索キーワードと流入経路
これらを把握せずに「デザインを変えれば成果が出る」と思い込むのは危険です。むしろ、データに基づく改善提案を出せる制作会社を選ぶことが、成功の第一歩になります。
データに基づかない判断
見た目や感覚だけで「このページはいらない」「内容を短くしよう」と決めるのは典型的な誤りです。実際に流入しているページを削除すれば、SEO評価が下がるだけでなく、既存ユーザーのアクセス導線を失うことにもつながります。
リニューアルの方向性を決める前に、Googleアナリティクスやヒートマップの分析結果を必ず確認すること。どのページが価値を生んでいるのかを把握しなければ、設計段階の議論が成り立ちません。
SEO対策を軽視した
SEOを無視したリニューアルは、最も深刻な“見えない失敗”を引き起こします。検索流入が減ると、見た目は美しくなっても、ユーザーがサイトを訪れる機会そのものが減ってしまうからです。
リダイレクト設定の失敗
旧URLと新URLの対応関係をきちんと整理せず、リダイレクトを設定しないまま公開してしまう。これにより、旧URLに貼られていた外部リンクやSNS投稿が404エラーとなり、評価がリセットされます。
防止策:リニューアルの初期段階で「URLマッピング表」を作り、すべての旧ページを新ページへ正確に301リダイレクトすること。
この作業を怠ると、どれほど良いコンテンツを作ってもSEOの基盤を失います。
コンテンツの大幅削除
Googleは情報量と専門性を重視します。したがって、リニューアルでページを統合・削除しすぎると、「このサイトは情報が減った」と判断され、順位が下がります。コンテンツを整理する際は、削除よりもリライト・再構成を優先するのが基本です。
noindexタグの消し忘れ
開発段階で検索エンジンにインデックスされないよう設定した「noindexタグ」を、本番公開後に削除し忘れる。この初歩的ミスによって、公開後も検索に一切出てこないという致命的なトラブルが起きます。
社内の連携不足
リニューアルは一部署だけでは完結しません。マーケティング、営業、広報、採用、経営――多くの部署が関係するため、連携不足は重大なリスクになります。
関係者の意見調整ができない
部署ごとに「デザインを重視したい」「問い合わせを増やしたい」「採用ページを拡充したい」と目的が異なる。そのままプロジェクトを進めると、結果的に中途半端なサイトになります。
対策:最初に「全体のKGI」を設定し、それに基づいたKPIを各部署に割り振ること。たとえば、全体目標を「問い合わせ件数20%増」に設定すれば、デザイン・採用・広報もその指標に沿って動けます。
制作会社とのコミュニケーション不足
発注側が「任せきり」にすると、制作会社は最低限の仕様だけで設計を進めます。仕様確認や中間レビューを怠ると、納品後に「想定と違うデザイン」や「機能が不足している」などのトラブルが発生します。リニューアルの成功率は、発注者がどれだけ積極的に関わるかで決まるといっても過言ではありません。
制作会社に丸投げした
「プロに任せれば安心」という考えは誤解です。制作会社は要件をもとに最適な形を提案しますが、事業理解や顧客層までは把握していません。したがって、発注側が情報提供を怠れば、成果の出ないリニューアルになります。
発注時には、次の3つを明確に伝えましょう。
- 1.自社の強みと競合との差別化要素
- 2.主要ターゲット(年齢層・地域・業種)
- 3.リニューアルの目的(ブランディング・集客・採用など)
これらを具体的に共有することで、制作会社は戦略的に設計できます。
リニューアル後の運用計画がない
公開後に「更新できない」「アクセス分析をしていない」というケースが非常に多いです。サイトは公開した瞬間から劣化が始まります。情報が古くなり、リンクが切れ、デザインが時代遅れになる。これを防ぐには、継続的な運用と改善の体制を整えることが不可欠です。
運用計画には以下を含めます。
- ・月次アクセスレポートの作成
- ・SEO順位のモニタリング
- ・コンテンツリライトのスケジュール化
- ・技術保守(CMS更新・SSL更新・サーバー監視)

SEO流入が激減するケース
リニューアルの影響でSEO流入が激減することは少なくありません。特に、公開直後の1か月で流入が30〜50%減少することもあります。
クロール拒否設定のミス
robots.txtに「Disallow: /」を残したまま公開すると、全ページがクロール拒否になります。Googleがサイトを認識しなくなるため、検索結果から一気に消えます。本番公開前には、必ずクロール許可設定を確認しましょう。
内部リンクの大量削除
リニューアルでメニュー構成を整理した際に、リンク数を減らしすぎるとSEOが悪化します。Googleは内部リンクをもとにページの重要度を判断するため、リンクを削除しすぎると評価が分散します。主要ページへ複数経路でアクセスできる構造を維持することが大切です。
titleタグの不適切な変更
リニューアルで「シンプルにしたい」とtitleを一新すると、SEOに悪影響が出ます。とくに上位表示ページでは、旧titleに含まれていたキーワードが評価要因になっていることが多く、削除すると順位が下がります。旧titleと新titleの差分を確認し、重要キーワードは残す設計を行いましょう。

ユーザビリティが悪化するケース
リニューアル後に「なんだか使いにくい」「迷いやすくなった」と感じるユーザーが増える場合、それは設計上の問題です。
デザイン重視で使いやすさを軽視
おしゃれなサイトを目指すあまり、情報を画像化してしまう。文字が読みづらい、ボタンが小さい――そんな細かなUXの欠点が積み重なると、離脱率が増えます。リニューアルは「美しさ」ではなく「成果を生む操作性」がゴールです。
既存ユーザーの慣れを無視した変更
長年使われていたサイトには、ユーザーの“慣れ”があります。たとえばログインボタンの位置が変わっただけで、問い合わせ件数が下がることもあります。主要導線(お問い合わせ・予約・購入)は位置や動作を大きく変えず、段階的に移行するのが理想です。
フォームの入力項目増加
フォーム項目を増やすと、送信率が下がることは多くの調査で証明されています。必要最低限の情報に絞り、入力補助やオートコンプリートを導入することで、CVRを維持できます。

リニューアル失敗を防ぐための対策
失敗を防ぐには、目的定義・分析・設計・検証の4ステップを確実に踏むことが重要です。
明確な目的とKGI・KPIを設定する
目的が不明確なリニューアルは方向を誤ります。サイトを通じて何を達成したいのか、数値で定義することが必須です。たとえば「月間問い合わせ50件」「採用応募率2倍」「SEO流入30%増」など。これにより、制作・デザイン・コンテンツの優先順位が明確になります。
現状分析を徹底する
リニューアル前にデータを分析しなければ、改善の方向性が決まりません。アクセス解析・ヒートマップ・アンケートなどを組み合わせて、問題点を可視化します。「なぜ成果が出ていないのか」を突き止めてから再設計に入ることが重要です。
SEOの知見がある制作会社を選ぶ
SEOを理解していない制作会社では、どんなにデザインが良くても結果が出ません。選定時には、過去のSEO成果・専門スタッフの有無・リニューアル後のサポート範囲を確認しましょう。
段階的なリニューアルを検討する
大規模サイトほど、一気に全ページを刷新するとリスクが高まります。まず主要ページだけを先行公開し、効果を測定した上で残りを移行する「段階的リニューアル」を推奨します。これにより、SEOやユーザー行動をモニタリングしながら安全に最適化できます。
公開前に十分なテストを行う
リリース直前の確認不足は、大きな損失につながります。リンク切れ、フォーム不具合、SEO設定ミスなどを防ぐために、チェックリストを複数人で運用することが大切です。特にrobots.txtやnoindexタグ、meta情報の再確認は必須項目です。

リニューアルを成功に導くための体制と進行管理
サイトリニューアルを「成功」で終わらせるためには、デザインやSEOだけでなく、プロジェクト全体の体制づくりと進行管理が重要です。
ここでは、リニューアルの裏側で見落とされがちな「組織面・運用面の成功要因」を解説します。
成功するリニューアルに共通する3つの体制設計
多くの成功事例を分析すると、どの企業にも共通する3つの仕組みがあります。それは、意思決定体制の明確化・情報共有の仕組み・検証と改善のループです。
1. 意思決定体制を明確にする
リニューアルは社内の多部署が関わるため、意思決定が曖昧になると方向性がぶれます。「デザイン優先か」「SEO優先か」「ブランディング重視か」――この優先度が決まっていないと、制作会社も判断できません。プロジェクトリーダーを1名指名し、最終決裁権を持つ責任者を明確にすることが必須です。会議ごとに意見が変わるような環境では、どれほど優秀な制作会社でも成果を出すことはできません。
2. 情報共有の仕組みを整える
リニューアルは情報量が多く、関係者間の齟齬が起きやすい業務です。SlackやBacklogなどのツールを使い、議事録・デザイン・要件変更を一元管理することで、誤認識を防げます。メールだけでやり取りを続けると、重要な情報が埋もれ、後から「言った・言わない」のトラブルになります。進行管理ツールを導入し、制作会社・社内担当・外注ライターの全員が同じ情報を見られる状態にしましょう。
3. 検証と改善のループを前提にする
「公開して終わり」ではなく、「公開して検証する」文化を根付かせること。アクセス解析・ユーザー行動データ・フォーム離脱率などを定期的に見直し、数字に基づく改善提案を続けるチーム体制を構築します。
プロジェクトを円滑に進めるスケジュール設計
リニューアルの失敗原因のひとつに「スケジュールの遅延」があります。納期が迫ると確認作業が省略され、品質が落ち、結果的にリリース後の修正コストが増えます。
フェーズごとの一般的なスケジュール例
- 1.企画・要件定義(2〜4週間)
現状分析・目標設定・要件整理を行う期間。ここで方向性を決める。 - 2.構成設計・デザイン(4〜6週間)
ワイヤーフレーム・デザイン案・サイトマップを制作。社内承認を得る。 - 3.開発・実装(4〜8週間)
コーディング・CMS構築・SEO設定・フォーム設計。 - 4.検証・テスト(2〜3週間)
リンクチェック、速度計測、SEO・UX確認を行う。 - 5.公開・効果測定(継続)
リリース後、最低3か月間のモニタリング期間を設け、改善サイクルを回す。
このスケジュールを守るには、タスク管理の徹底とリスクの早期共有が不可欠です。「想定外の修正が発生したら納期を再調整する」など、柔軟なマネジメントも重要です。
リニューアルを失敗させない社内教育と役割分担
プロジェクトがうまくいくかどうかは、チーム内の理解度に左右されます。「担当者が交代した」「Webの専門知識がない」「意思決定者が技術用語を理解していない」といった理由で、議論が空回りすることもあります。
教育・共有のポイント
- ・社内勉強会を実施し、リニューアルの目的とKPIを全員が理解する
- ・デザイン案・構成案の意図を制作会社から直接説明してもらう
- ・SEOやUIの基礎用語を社内で共有し、判断の基準を統一する
これにより、“なんとなく良さそう”ではなく“なぜそれが必要か”を全員が理解して判断できる組織になります。
役割分担を明確にする
リニューアルには多くの関係者が関わります。プロジェクトリーダー、ライター、デザイナー、エンジニア、社内承認者――それぞれの役割と責任を明確にすることが、最終的な品質を左右します。とくに「承認者が多いほど進行が遅れる」ことを意識し、最終決定ラインを一本化するのが成功のコツです。
成功企業に共通する“リニューアル後3か月の動き”
リニューアル直後は、アクセスや問い合わせが一時的に減ることもあります。ここで焦らず、データの変化を分析し、改善に反映させる企業こそが成功します。成功企業が行っている3か月間の基本施策を紹介します。
- 1.1か月目:初期データの収集
アクセス数、離脱率、クリック位置を把握し、想定とのギャップを確認する。 - 2.2か月目:A/Bテストの開始
ボタン色、CTA位置、見出し文言を複数パターン検証し、成果が出やすいデザインを特定。 - 3.3か月目:SEOと導線の微調整
インデックス数・検索順位の変化を確認し、低下ページをリライト・リンク補強する。
この3ステップを確実に実行できれば、リニューアルの投資効果は半年後に明確な成果として表れます。
コンテンツ運用チームの構築と継続改善
リニューアルは終わりではなく、始まりです。本当の勝負は公開後に始まるコンテンツ戦略の継続力です。
コンテンツPDCAを内製化する
- ・Plan(計画):ユーザーの課題を定義し、テーマを設定
- ・Do(実行):記事制作・投稿
- ・Check(検証):アクセス・滞在時間・検索順位を分析
- ・Act(改善):リライト・導線変更・新コンテンツ追加
これを社内で回せる体制を持つ企業は、外注依存の企業よりも圧倒的に成果を出しています。分析と改善を繰り返す中で、ユーザー理解が深まり、ブランドとしての一貫した発信力が育ちます。
制作会社との共創体制を築く
リニューアル後も、制作会社を単なる外注先ではなく「共創パートナー」として関係を続ける企業が増えています。月次レポートをもとに改善提案を受け、PDCAを一緒に回す。これにより、内部リソースだけでは得られない専門知識を活用し、常に最新のSEO・UXトレンドを反映できます。
DX・AI時代のリニューアル戦略
近年はAIツールの進化により、リニューアルの在り方も変わってきています。生成AIを活用して、コンテンツ設計・キーワード分析・構成案作成を効率化する企業も増えています。しかし、AIが出力する文章は「事実精度」や「トーン整合性」に課題があるため、人間の監修が不可欠です。最も理想的なのは、AIを「補助ツール」として使い、専門知識と体験価値を人間が補うハイブリッド運用です。この考え方を早期に取り入れた企業ほど、コンテンツ制作スピードを上げながら品質を維持しています。
社内外の一体感が成功を生む
リニューアルの本質は、単なる「Webデザイン」ではなく、企業の意志を形にする再構築です。経営者・現場担当・制作会社・ライター――それぞれの立場が同じゴールを共有できたとき、初めて真の成功が訪れます。
プロジェクトをチームの挑戦として共有し、“誰のために変えるのか”という視点を持ち続けることが、最終的に最も強い成果につながります。

まとめ
サイトリニューアルは成功すれば企業価値を高めますが、失敗すれば信頼と流入を失います。失敗を防ぐ鍵は、明確な目的・データ分析・SEO設計・社内連携・検証体制です。本記事で紹介した内容をもう一度整理すると、次の通りです。
- 1.現状分析を徹底し、データに基づく判断を行う
- 2.301リダイレクトで評価を引き継ぐ
- 3.コンテンツは削除せず再構成で残す
- 4.UXを重視し、ユーザー視点の設計を行う
- 5.公開後も運用・分析を継続する
これらを実行すれば、「見た目だけのリニューアル」から「成果を出すサイト」へ進化できます。

東海((岐阜・愛知・名古屋・三重))でサイトリニューアルを依頼するならGRASPERS
当社GRASPERSは、岐阜・東海地域を中心に、成果を重視したサイトリニューアル支援を提供しています。単なるデザイン変更ではなく、「アクセスが増え、問い合わせが増える」リニューアルを実現します。
- ・SEO戦略設計と実装
- ・ユーザビリティ最適化
- ・Core Web Vitals対応の高速化
- ・CMS構築と保守運用サポート
- ・リニューアル後の定期分析と改善提案
当社GRASPERSでは、現状分析から戦略立案、設計、制作、運用までワンストップで支援します。リニューアル後も成果を維持・拡大するパートナーとして、長期的な成長を支えます。岐阜・愛知・三重・静岡エリアで、サイトリニューアルに失敗したくない企業様は、ぜひ一度ご相談ください。あなたのビジネスを、確実に“成果が出るWebサイト”へ導きます。当社と一緒に未来を創造しましょう!



