SEO対策のキーワード選定で成果を出す実践手順

SEO対策を始めるうえで、最初に直面する壁が「どんなキーワードを選ぶべきか」という問題です。検索エンジンで上位表示を目指すためには、単に人気のある言葉を狙えばよいというわけではありません。「SEO対策 キーワード 選定」こそ、成果を出すための最重要ステップです。
検索エンジンに評価される記事を作るためには、まず「ユーザーがどんな目的で検索しているのか」を理解することが欠かせません。たとえば、同じ「SEO対策」という言葉でも、「仕組みを知りたい人」「費用を知りたい人」「自分でやりたい人」では検索意図が異なります。この意図を正確に読み取らないまま記事を作成すると、検索順位が上がっても成果(問い合わせ・購買)に結びつかないケースが多くなります。
つまり、SEOにおけるキーワード選定とは、単なる“言葉探し”ではなく、ユーザーの思考を可視化し、企業の発信を最適化する戦略設計なのです。
この記事では、SEO初心者から中級者までを対象に、「SEO対策のキーワード選定」を正しく行い、実際に成果を上げるための手順を体系的に解説します。まずは基本的な考え方として、「キーワード選定がなぜSEOの成功を左右するのか」を明らかにし、次に検索意図の分析、ボリュームと競合性の評価、そして実際の選定手順(6ステップ)を詳しく紹介します。
さらに、Googleキーワードプランナー・ラッコキーワード・Ahrefs・SEMrushなど、初心者からでも使えるツールの活用方法を具体的に解説。加えて、「検索ボリュームだけで判断してはいけない理由」「選定キーワードを記事に反映する方法」など、実務でつまずきやすいポイントもわかりやすく整理しています。
SEOの成果は、キーワードの精度で決まります。どれほど優れたコンテンツを作っても、検索意図からズレた言葉を選んでいては評価されません。
この記事を通じて、「感覚ではなく戦略で選ぶキーワード選定」の考え方を身につければ、あなたのWebサイトは長期的に成長し、安定した集客基盤を構築できるはずです。

目次
SEOキーワード選定の基礎知識
SEO対策の第一歩は、どのキーワードで戦うかを決めることです。どれほど質の高い記事を作っても、ユーザーが検索しない言葉を狙っていては意味がありません。
逆に、適切なキーワードを選べば、比較的少ない労力でも自然検索から継続的なアクセスを得ることが可能です。
SEOの本質は「検索ユーザーの意図を満たすこと」にあります。
そのため、キーワード選定とは単なるリサーチ作業ではなく、ユーザー心理を分析し、ビジネス目標と結びつける戦略的行為だといえます。
キーワード選定がSEO成功を左右する理由
Googleの検索エンジンは、ユーザーが入力した「検索クエリ(検索語句)」をもとに、最も関連性が高いページを表示します。したがって、記事内容と検索語句の一致度が高いほど、検索上位に表示される確率が上がります。
しかし、多くのサイト運営者がここで誤解しているのは、「アクセス数の多いキーワード=成果が出る」と考えてしまう点です。実際には、アクセス数よりも「検索意図との一致度」こそが成果を決める最重要要素です。
たとえば、次の2つのキーワードを比較してみましょう。
- ・「SEO 対策」:検索数が非常に多いが、競合が強く上位表示が難しい
- ・「SEO 対策 キーワード 選定」:検索数は少ないが、明確な課題意識を持ったユーザーが多い
後者のように検索意図が明確なキーワードのほうが、コンバージョン(成果)につながる確率が高いのです。
つまり、「検索ボリュームよりも意図の精度を重視する」という考え方が、SEO成功の第一歩となります。
検索意図の把握と分析手法
キーワード選定を正しく行うためには、ユーザーの「検索意図(Search Intent)」を理解する必要があります。検索意図とは、ユーザーがなぜそのキーワードで検索したのかという背景のことです。
SEOで上位表示を狙うには、この検索意図に的確に応えるコンテンツを作ることが欠かせません。
そのために、まずは検索意図の種類を把握しておきましょう。
| 検索意図の分類 | 意味 | 代表例 |
|---|---|---|
| 情報取得型(Informational) | 知識や情報を得たい | 「SEOとは」「SEO対策 方法」 |
| 比較検討型(Navigational) | 選択肢を比較・検討したい | 「SEO会社 比較」「SEO ツール おすすめ」 |
| 取引型(Transactional) | 申し込み・購入など行動を起こしたい | 「SEO代行 費用」「SEO サービス 依頼」 |
顕在ニーズと潜在ニーズの見極め方
SEOキーワード選定では、検索意図とあわせて「ニーズの顕在・潜在」も把握する必要があります。
- ・顕在ニーズ:明確な課題を認識し、解決策を探している状態
例:「SEO対策 料金」「SEO 業者 選び方」 - ・潜在ニーズ:自覚はしていないが、課題の存在を感じている状態
例:「アクセスが増えない」「ホームページ 集客 伸ばす方法」
多くの企業サイトは顕在ニーズ向けのキーワードばかりを狙いがちですが、実際にコンバージョン(問い合わせ・購入)につながりやすいのは潜在ニーズ型キーワードです。理由は、ユーザーがまだ情報を探している段階で接点を持つことで、信頼関係を築けるからです。
検索クエリの種類と特徴
検索クエリ(Search Query)とは、ユーザーが検索エンジンに入力する言葉の組み合わせのことです。
同じテーマでも、入力されるクエリによって意図や文脈が異なります。
- ・「SEO 対策 キーワード 選定」 → 情報収集段階(知りたい)
- ・「SEO キーワード 選定 ツール」 → 実践段階(使いたい)
- ・「SEO キーワード 選定 代行」 → 発注検討段階(依頼したい)
このように、検索クエリはユーザーの購買ステップを映し出す鏡です。
そのため、コンテンツ設計の際は、検索クエリの段階に応じた記事内容を用意する必要があります。
キーワードの種類と難易度
SEOキーワードは、検索ボリューム(検索回数)や競合性の高さによって以下の3種類に分類されます。
| 種類 | 検索回数の目安 | 特徴 | 難易度 |
|---|---|---|---|
| ビッグキーワード | 月1万回以上 | 検索数が多く、競合が非常に多い | 高い |
| ミドルキーワード | 月1,000〜9,999回 | 検索意図が明確で成果につながりやすい | 中程度 |
| ロングテールキーワード | 月1,000回未満 | ニッチで競合が少なく、成約率が高い | 低い |
初心者や中小企業サイトが狙うべきは、ロングテールキーワードです。
たとえば、「SEO 対策 キーワード 選定 方法」「SEO 対策 ワードプレス 設定」といった複合キーワードが該当します。こうしたキーワードは競争が少なく、短期間で成果を出しやすいのが特徴です。
検索ボリュームと競合性の関係
キーワードを評価する際、最も多くの人が参考にするのが「検索ボリューム」ですが、実はこれだけでは不十分です。検索数が多いキーワードはアクセスを集めやすい一方で、競争も激しく、上位表示には時間とコストがかかります。
一方、検索数の少ないキーワードは上位表示が早く、成約率が高い場合も多いのです。
以下のように目的によって戦略を分けるとよいでしょう。
- 1.アクセスを増やす目的 → ミドル〜ビッグキーワードを狙う
- 2.成果を上げる目的 → ロングテールキーワードを中心にする
SEOで大切なのは「アクセス数」ではなく「成果数」です。数千人が来ても売上につながらなければ意味がなく、少数でも意図の合致したユーザーを集めることこそが真のSEO成功です。
ここまでで、SEO対策の基本となるキーワード選定の考え方・種類・分析方法を理解できました。次の第2段階では、実際にどのようにキーワードを洗い出し、整理し、優先順位を付けるかという「キーワード選定の実践6ステップ」を詳しく解説していきます。

キーワード選定の実践6ステップ
SEO対策において「キーワード選定」は理論で終わらせず、明確な手順で実践することが重要です。ここでは、実際に成果を上げるための6つのステップを順を追って解説します。初心者でもすぐに実践できるよう、具体的な方法とツールの使い方も紹介します。
ステップ1:サイトの目的とペルソナ設定
SEO対策の出発点は、単にキーワードを探すことではなく、サイトの目的を定義することです。なぜなら、目的が曖昧なままでは、どの検索意図を狙うべきかが決まらないからです。
たとえば次のように、Webサイトのタイプによって狙うキーワードはまったく異なります。
| サイトのタイプ | 目的 | 狙うべきキーワード例 |
|---|---|---|
| コーポレートサイト | 信頼性の向上 | 「会社名+サービス」「企業理念」 |
| 集客ブログ | 新規リード獲得 | 「SEO 対策 キーワード 選定 方法」 |
| ECサイト | 購入促進 | 「商品名+口コミ」「購入+比較」 |
コンテンツの目的を明確化する方法
まずは、自社サイトのゴールを一文で定義してみましょう。
「このページを読む人に、何をしてもらいたいのか?」を明確にすると、適切なキーワードが見えてきます。
- ・「SEO対策を学びたい人に、基本的な考え方を理解してもらう」
- ・「キーワード選定の方法を調べている人に、実践手順を示す」
このように目的が明確であれば、狙うべき検索意図が自ずと定まります。
悩みベースのペルソナ設定
次に、想定読者(ペルソナ)を設定します。ペルソナとは、サービスを利用する“架空の顧客像”のことです。
SEOでは、検索者の悩みや知識レベルを理解することで、より適切なキーワードを選定できます。
- ・名前:田中さん(30代・中小企業の広報担当)
- ・悩み:「ホームページを作ったがアクセスが伸びない」
- ・検索行動:「SEO 対策 初心者」「SEO キーワード 選定 方法」などで検索
このように具体的に描くことで、コンテンツの方向性とキーワードの粒度を調整しやすくなります。
ステップ2:メインキーワードの決定
サイトの目的とターゲットが明確になったら、次は「メインキーワード」を決めます。メインキーワードとは、コンテンツ全体の中心となる言葉であり、Googleがページ内容を理解するための軸です。
たとえば本記事であれば「SEO 対策 キーワード 選定」がメインキーワードに該当します。メインキーワードは1記事につき1つに絞ることが原則です。
複数のテーマを1つの記事で扱うと、焦点がぼやけて評価されにくくなります。
一方、明確な主軸キーワードを設定することで、内部リンクの設計やコンテンツ設計も一貫性を持たせることができます。
ステップ3:関連キーワードの洗い出し
メインキーワードが決まったら、次に関連語句を洗い出します。Googleは単語単位ではなく「文脈(コンテキスト)」でページを評価するため、関連する用語を自然に含めることが重要です。
関連キーワードを調べる方法は大きく2つあります。
サジェストキーワードの活用法
Google検索窓にメインキーワードを入力すると、自動で候補語(サジェスト)が表示されます。これが実際に検索されている関連語であり、リアルなユーザーニーズを反映する貴重な情報です。
・「SEO 対策 キーワード 選定」と入力した場合
・「SEO 対策 キーワード ツール」「SEO 対策 キーワード 表」「SEO 対策 初心者」など
これらを参考に、「どんな悩み・目的で検索しているのか」を分析し、記事の方向性を決定します。
関連キーワードツールの使い方
より体系的に抽出したい場合は、以下の無料ツールが便利です。
| ツール名 | 特徴 |
|---|---|
| ラッコキーワード | Googleサジェストを自動抽出。ボリューム把握にも最適。 |
| キーワードプランナー | 広告向けツールだが、月間検索数・競合性が確認できる。 |
| Ubersuggest | 競合サイトが狙うキーワード分析にも対応。 |
これらを組み合わせることで、「検索されやすく、競合が少ない」キーワード群を効率的に見つけ出すことができます。
ステップ4:検索ボリュームと競合分析
関連キーワードが集まったら、それぞれの「検索ボリューム(需要)」と「競合性(難易度)」を評価します。
この2つを比較することで、狙うべき優先度が明確になります。
上位表示可能性の見極め方
- ・検索ボリューム:月間1,000回未満 → ねらい目
- ・競合性:中〜低 → 実践的な成果が出やすい
SEOでは、「難易度×成果可能性」のバランスを取ることが重要です。大手サイトが独占している領域ではなく、自社ならではの強みを活かせるニッチキーワードを選びましょう。
競合サイトの構成分析
キーワードごとに検索上位10サイトを確認し、次の要素を比較します。
- 1.タイトルと見出し構成
- 2.コンテンツの文字数・深さ
- 3.画像・動画などの使用状況
- 4.内部リンクや導線の作り方
これらを分析することで、「自社がどの観点で差別化できるか」が見えてきます。
特にWordPressを利用している場合、内部リンクやタグ設計を見直すだけでもSEO評価が大きく変わることがあります。
ステップ5:キーワードのグルーピング
抽出したキーワードは、テーマや検索意図ごとにグルーピングして整理します。同じ意味を持つ語句をまとめることで、記事構成をスムーズに設計でき、カニバリゼーション(重複評価)も防げます。
- ・「SEO 対策 キーワード 選定」「SEO キーワード 選び方」→ 同グループ
- ・「SEO 対策 ツール」「SEO 分析 ソフト」→ 別グループ
表計算ソフトを使って分類しておくと、記事制作時の指針になります。
ステップ6:優先順位付けと管理
最後に、グルーピングしたキーワードを「成果につながる順」に並べ替えます。優先度は以下の3要素で評価します。
| 評価項目 | 内容 | 重要度 |
|---|---|---|
| 検索意図の一致度 | 自社の目的にどれだけ近いか | 高 |
| 検索ボリューム | 潜在的なアクセス数 | 中 |
| 競合性 | 上位表示の難易度 | 中〜低 |
この段階で、狙うキーワードと記事タイトルの対応表を作成しておくと、
SEOコンテンツ戦略を長期的に運用しやすくなるでしょう。

効果的なキーワード選定ツール活用法
SEO対策では、ツールを上手に使うことでリサーチ効率が格段に上がります。ここでは、無料・有料の主要ツールを紹介し、それぞれの得意分野と使い分け方を解説します。
無料ツールの特徴と使い分け
- 1.Googleキーワードプランナー
広告運用だけでなく、SEOキーワード分析にも活用可能。
検索ボリューム・競合性・関連語を一括取得できます。 - 2.ラッコキーワード
Googleサジェストをまとめて取得でき、リアルなユーザー意図を把握するのに最適です。 - 3.サーチコンソール
自社サイトの実際の検索クエリを分析可能。CTR(クリック率)と順位を掛け合わせて改善に役立ちます。
有料ツールで得られる追加価値
無料ツールでは把握しづらい「競合データ」や「被リンク分析」は、有料ツールでカバーできます。
- ・Ahrefs:競合の上位記事・被リンクを可視化
- ・SEMrush:キーワードの難易度やトレンドを長期的に追跡
これらを併用すれば、「どのキーワードを狙えば最短で上位表示できるか」が数値で判断可能になります。

キーワード選定後のコンテンツ戦略
キーワード選定が完了したら、次の段階は「選定したキーワードをどう活かすか」です。
SEO対策はキーワードを決めて終わりではなく、そのキーワードを中心にどのようなコンテンツを作るかで結果が決まります。
選定キーワードを活かした記事構成
コンテンツ制作の第一歩は、選定したキーワードをもとにした「記事設計」です。記事設計では、以下の3点を意識します。
- 1.検索意図を満たす内容になっているか
- 2.読者が知りたい順番で情報が並んでいるか
- 3.キーワードが自然に使われているか
たとえば「SEO 対策 キーワード 選定 方法」というキーワードで記事を書く場合、冒頭では「なぜキーワード選定が必要か」を説明し、続いて「ツールの使い方」「実践手順」「注意点」という流れにするのが自然です。
検索意図を軸に構成を設計すると、読者満足度も検索評価も高まります。
タイトルとメタディスクリプションの最適化
SEOで最も重要な要素の一つがタイトルタグとメタディスクリプションです。これらは検索結果に直接表示され、クリック率を左右します。
- ・タイトル:メインキーワードを左側に配置し、30文字以内で完結
例:「SEO対策のキーワード選定方法|初心者でもできる6ステップ」 - ・メタディスクリプション:100〜120文字で要約し、検索意図に合ったベネフィットを提示
例:「SEO対策の成果はキーワード選定で決まります。本記事では実践的な6ステップを具体例付きで解説します。」
これにより、検索ユーザーのクリックを誘発しやすくなります。
見出し構成への反映方法
見出し(h2、h3、h4)には、キーワードや関連語を自然に組み込むことが重要です。
見出しにキーワードを入れることで、Googleがページの主題を正確に把握できます。
- ・h2:「SEO対策のキーワード選定とは?」
- ・h3:「Googleに評価される選定基準」
- ・h4:「初心者でもできるリサーチ手順」
見出し=検索意図を満たす小さな答えの集まりと考えると、構成が作りやすくなります。
一次情報を含めた差別化戦略
現在のSEOでは、単なる情報のまとめ記事では上位表示が難しくなっています。
Googleは、「独自性の高い一次情報」を重視しており、体験談や調査データ、現場の声などを盛り込むことが評価されやすい傾向にあります。
- ・自社で行った分析データ
- ・専門家やクライアントのコメント
- ・実際の改善事例や数値
こうした独自の視点を取り入れることで、競合との差別化が可能になります。同じ「SEO 対策 キーワード 選定」をテーマにしても、自社の経験を交えるだけでオリジナリティと信頼性が格段に向上します。
カニバリゼーション回避のポイント
複数の記事で似たようなキーワードを狙うと、Googleがどのページを評価すべきか判断できず、順位が下がる「カニバリゼーション」が発生します。
これを防ぐには、以下の2点を意識しましょう。
- 1.同一テーマの記事を1本に統合する
- 2.内部リンクで主従関係を明確にする
たとえば、「SEO キーワード 選定」と「SEO キーワード ツール」を別記事にしたい場合、前者を「戦略的な選定方法」として軸に置き、後者を「補足記事」として内部リンクで関連付けます。
このように役割を整理することで、サイト全体の構造が明確になり、評価が分散しません。
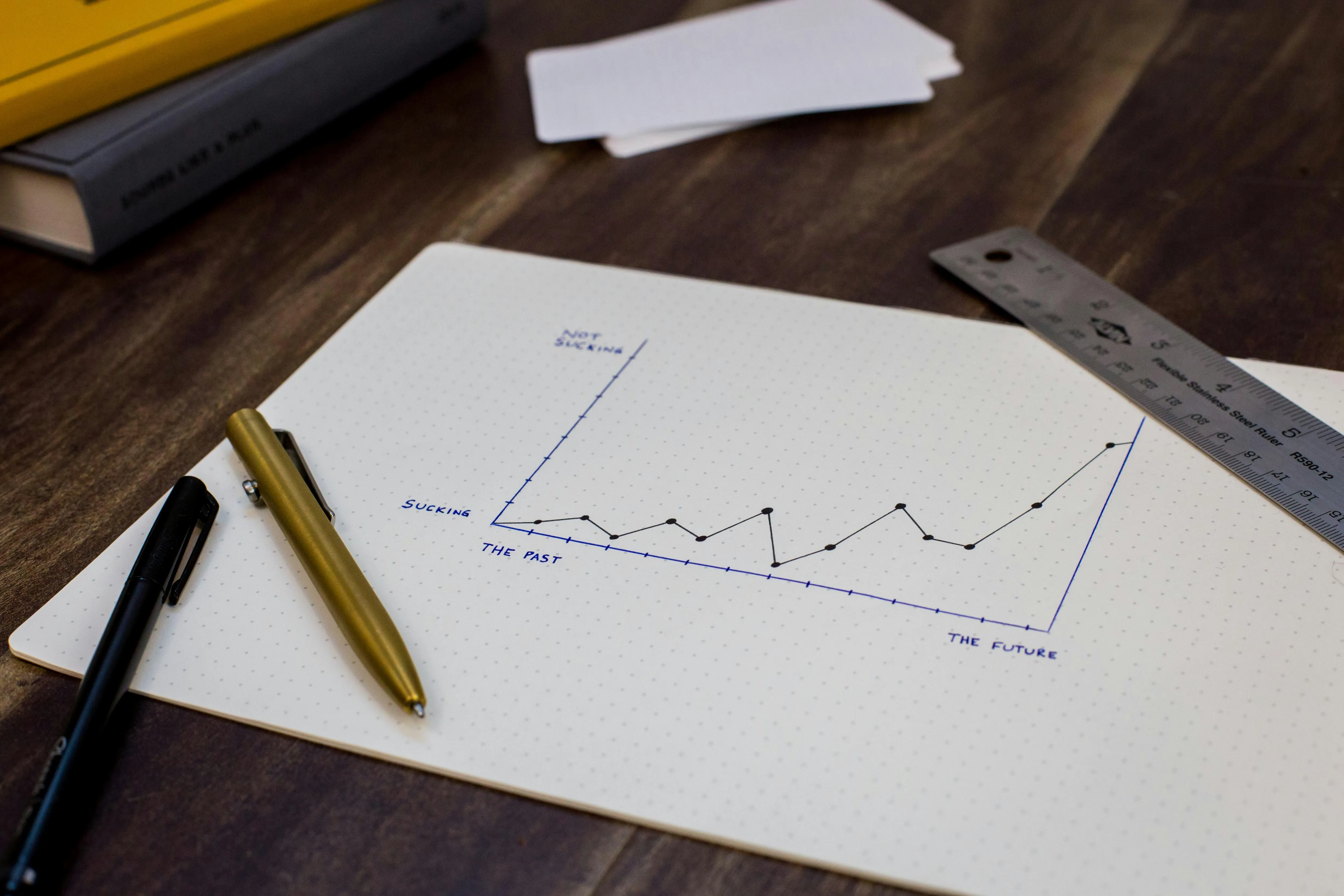
キーワード選定でよくある失敗と対策
SEO初心者の多くが、キーワード選定で次のような落とし穴に陥ります。ここでは、失敗パターンとその対策を具体的に紹介します。
検索ボリュームだけで判断する危険性
キーワード選定において最も多い誤りが、「検索数が多いキーワード=良いキーワード」と思い込んでしまうことです。確かに、検索ボリュームが大きいほどアクセスが集まりやすく見えます。しかし実際には、検索ボリュームの多さが成果を保証するわけではありません。むしろ、多くの企業がこの考え方のせいでSEOに失敗しています。
たとえば、「SEO 対策」や「ホームページ 作り方」といったビッグキーワードは、月間で数万回以上検索されています。しかし、その上位には大手企業・専門メディア・広告主が多く、ドメインパワー・被リンク・ブランド力の差が圧倒的です。新規ドメインや中小企業がこのようなキーワードで上位表示を狙うのは、予算・時間・リソースの面で極めて非効率です。実際、上位表示に半年〜1年以上かかるケースも珍しくありません。
一方、「SEO 対策 キーワード 選定」「SEO 記事 構成」「SEO 内部 対策 方法」など、検索ボリュームが月間200〜500程度の“ロングテールキーワード”では、競合が減り、ユーザーの目的も明確です。これらは購買意欲が高く、成約率(CVR)が高いユーザー層に届きやすいのが特徴です。検索ボリュームが少なくても、狙った顧客に直接届くため、結果的に売上・問い合わせ数の向上につながるケースが多いのです。もう少し具体的に言えば、SEOの目的は「アクセス数を増やすこと」ではなく、「適切なユーザーを集め、成果につなげること」です。
たとえば次のような違いがあります。
| キーワード | 月間検索数 | 意図 | 難易度 | 成果へのつながり |
|---|---|---|---|---|
| SEO 対策 | 約10,000 | 一般的な情報収集 | 非常に高い | 低い |
| SEO 対策 キーワード 選定 | 約300 | 実践手順・改善策を探している | 中 | 高い |
| SEO 記事 書き方 | 約200 | 実務的な方法を知りたい | 中 | 高い |
このように、検索ボリュームが多いキーワードほど「意図が曖昧」で、結果的にコンバージョンにつながらないケースが多いのです。逆に、検索ボリュームが小さいキーワードのほうが「目的が明確」なユーザーが集まり、実際の成果率が高くなる傾向があります。
もう一つのポイントは、「ボリュームの数字は常に変動している」という事実です。Googleキーワードプランナーなどで表示される検索数は過去平均データであり、リアルタイムの検索動向とは異なる場合があります。たとえば、新しいトレンドワードや話題性の高いテーマは、ツール上で「月間10以下」と表示されていても、実際にはSNSやニュースをきっかけに急激に検索が増えているケースもあります。
したがって、ボリュームの数字は「目安」にすぎないと考え、検索意図や競合状況をセットで評価することが不可欠です。
判断の基準としては、次の3つを意識するとよいでしょう。
- 1.検索意図が明確であるか(具体的な行動や悩みに結びついているか)
- 2.競合サイトの質と規模はどうか(大手ばかりなら避ける)
- 3.自社がそのキーワードに対して提供できる価値があるか
たとえば、「SEO 外注 方法」というキーワードは検索数こそ1,000未満ですが、検索しているユーザーはすでに外注を検討している層です。つまり、記事を読んだあとに問い合わせへつながる可能性が高い“高コンバージョンキーワード”です。
このように、SEOでは「数字」よりも「意図」を重視することが大切です。検索ボリュームだけを基準に判断すると、結果的に競争の激しい市場に埋もれ、費用対効果の悪い施策になってしまいます。
本当に狙うべきは、「少ない検索でも、濃いユーザーが来るキーワード」です。これこそが、限られたリソースで最大の成果を出すための本質的なSEO戦略といえます。
自社視点でのキーワード選定の落とし穴
企業サイトにありがちな失敗が、「自社が使いたい言葉」でキーワードを決めてしまうこと」です。
ユーザーが実際に検索する言葉と、企業が使う専門用語は必ずしも一致しません。
たとえば、「検索順位改善サービス」という言葉を自社では使っていても、
ユーザーは「SEO 対策 依頼」や「SEO 外注 方法」で検索している場合があります。
したがって、キーワード選定は必ずユーザー目線で考えることが重要です。
サジェストや検索連想語を調べ、実際の検索習慣を基に選ぶようにしましょう。
キーワード選定の定期的な見直しの重要性
SEOの世界は変化が速く、Googleアルゴリズムの更新やトレンドの変化により、検索意図も日々変わります。
そのため、一度決めたキーワードを放置せず、定期的に見直すことが成功への近道です。
- 1.3〜6か月ごとに順位・CTRを確認する
- 2.検索ボリュームの変化をツールでチェック
- 3.新たに伸びている関連語を追加する
キーワードを継続的にメンテナンスすることで、サイト全体のパフォーマンスを安定的に維持できます。

まとめ
ここまで、「SEO対策におけるキーワード選定」の基礎から実践までを解説しました。改めて、成果を出すための要点を整理しましょう。
| ステップ | 内容 | 成功のポイント |
|---|---|---|
| ステップ①:方向性を定める | 目的とターゲットを明確にする | サイトの方向性を決めてからキーワードを探す |
| ステップ②:軸を決める | メインキーワードを1つ選ぶ | 一記事一テーマを徹底 |
| ステップ③:範囲を広げる | 関連キーワードを洗い出す | サジェストやツールを活用 |
| ステップ④:狙いを絞る | ボリュームと競合性を分析 | 狙える範囲を見極める |
| ステップ⑤:構造化する | グルーピングと整理 | 記事構成に活かす |
| ステップ⑥:行動に移す | 優先順位を付けて運用 | 成果に近いものから取り組む |
これらを体系的に行えば、SEO初心者でも安定した成果を得ることができます。特に、「SEO 対策 キーワード 選定」はすべてのSEO施策の基盤です。最初の設計を正しく行えば、後の運用・リライト・内部リンク戦略まですべてがスムーズに進みます。

東海((岐阜・愛知・名古屋・三重))でSEO対策を任せるならGRASPERS
SEO対策を実践する中で、「何から手を付けていいか分からない」「結果が出ない」と悩む企業は少なくありません。
そんな方々におすすめしたいのが、東海((岐阜・愛知・名古屋・三重))エリアでSEOとWeb制作に強い当社GRASPERS(グラスパーズ)です。
当社は、「戦略 × 制作 × 運用」を一体化したSEO支援を得意としています。
単に検索順位を上げるだけでなく、問い合わせ・集客・売上までつなげるSEOを目指しています。
GRASPERSの強み
- 1.地域特化型のSEOノウハウ
東海((岐阜・愛知・名古屋・三重))・愛知・三重など、地域検索に強いローカルSEOを得意としています。 - 2.WordPress制作とSEOの一括対応
構築から内部最適化・記事運用までを自社で完結。SEO内部構造を初期段階で設計します。 - 3.成果重視の運用サポート
GA4・Search Console分析を活用し、毎月の改善提案を実施。
導入実績の一例
| 業種 | 成果 | 期間 |
|---|---|---|
| 製造業(岐阜) | 検索流入2.3倍/商談数1.8倍 | 6か月 |
| 建設業(名古屋) | 「地域名+業種」で1位獲得 | 4か月 |
| サービス業(三重) | 問い合わせ数150%増 | 5か月 |
最後に
SEOは「短期的な施策」ではなく、中長期で積み上げる資産形成の手段です。
適切なキーワード選定を軸に、正しい方向で運用を続ければ、確実に結果がついてきます。
当社GRASPERSは、「自社でSEOを強化したい」「WordPressサイトを最適化したい」という企業様に最適なパートナーです。まずは無料相談から、あなたのビジネスに合ったSEO戦略を一緒に設計していきましょう。



